2019年06月30日
■創作劇『こころつないで』を、ふか~く楽しむために
■創作劇『こころつないで』を、ふか~く楽しむために(その13)
7.遺跡・遺物に表現された現実を知る
行政的には埋蔵文化財、一般に知られた言葉では遺跡を発掘調査していると、今から1500年ほど前の古墳の石室から鉄製の剣や鎧が出土することがあります。この時、「うわぁ~、何か宝ものが出た!」と耳にします。「宝モノ」と聞けば金財宝を思い浮かべますが、発掘調査をしていると金属製の遺物が出土することはあまりありませんので、そのような発想になることはいたしかたないのかもしれません。しかし、剣、鎧は、言い方をかえると武器・武具です。武器・武具があるということは争いがあったということは容易に想像がつきます。現代社会では、いわゆる銃刀法というものがあるので、武器そのものをお供えすることは禁じられていますが、親族の葬儀の際に武器そのものをお供えすることは少ないでしょう。それは、現代の日本が武器を必要とする社会ではないことの証ともいえます。
ここに、佐賀県にある特別史跡吉野ヶ里遺跡から出土した甕棺と人骨の写真があります。


●特別史跡吉野ヶ里遺跡検出の甕棺(佐賀県教育委員会、1990)
佐賀県教育委員会(1990)『環濠集落 吉野ヶ里遺跡 概報』より
頭のない人骨を埋葬した甕棺、矢じりが刺さったと考えられる人骨などは、何を物語っているのでしょうか。頭のない人骨は、いまでこそ語られることはなくなったと思いますが、かつては奴隷の墓と言われていました。「奴隷」、いいかえるとモノを言う道具といわれるほど、過酷な労働を強いられる階層の人々を指しています。そのような時代があったことは記憶に留めておく必要があります。このような過酷なまたは熾烈な階層の人々のために、製作に数日を要する甕棺を作ることや集落に共住する人々と同列の墓に埋葬されていることを考えると疑問が生じます。これは、何かの出来事に巻き込まれた親族の墓ではないかと想像できます。何かの出来事、そう、争いが容易に想像できます。ムラとムラの間で水争いや耕作地を巡る争いによって戦が起き、戦いの中で、首を切られてしまった仲間の墓だと想像できます。
このように、遺跡の発掘調査で明らかになることは、宝もの探しではなく、人々が生きてきた証を記録し、その時代に何が起こったのか、どのような社会だったのかを考える「証拠」を掴むため、無造作に掘り散らかすのではなく、一つひとつを丁寧に掘り、骨に刺さった小さな矢じり等、遺跡(埋蔵文化財)の記録保存のための発掘調査が行われているのです。
※竪穴住居の発明は、人々の行動範囲を広げ、土器の発明は食材の幅を広げ、幼子、病人、高齢者の食の幅を広げることに大きな貢献をします。稲などの穀物栽培は定住化を促進し、食の安定化と多世代の移住に要する労力を軽減します。
一方、穀物栽培に伴う定住化については、穀物栽培のための時間、ゴミや排泄物処理のための時間など、人々が従来持っていた自由な「時間」を拘束したという考えもあります。どちらが人類にとっていいことなのかは、その後の社会発展の状況から複合的に考えていかなければならないことです。「いいこと」もあれば、「悪いこと」もある。これらを、私たちを取り巻く社会の思想的な背景があり完全とはいえませんが、可能な限り恣意性を排除して観察し、未来に生かしていくことが歴史を学ぶ目的の一つなのです。
7.遺跡・遺物に表現された現実を知る
行政的には埋蔵文化財、一般に知られた言葉では遺跡を発掘調査していると、今から1500年ほど前の古墳の石室から鉄製の剣や鎧が出土することがあります。この時、「うわぁ~、何か宝ものが出た!」と耳にします。「宝モノ」と聞けば金財宝を思い浮かべますが、発掘調査をしていると金属製の遺物が出土することはあまりありませんので、そのような発想になることはいたしかたないのかもしれません。しかし、剣、鎧は、言い方をかえると武器・武具です。武器・武具があるということは争いがあったということは容易に想像がつきます。現代社会では、いわゆる銃刀法というものがあるので、武器そのものをお供えすることは禁じられていますが、親族の葬儀の際に武器そのものをお供えすることは少ないでしょう。それは、現代の日本が武器を必要とする社会ではないことの証ともいえます。
ここに、佐賀県にある特別史跡吉野ヶ里遺跡から出土した甕棺と人骨の写真があります。


●特別史跡吉野ヶ里遺跡検出の甕棺(佐賀県教育委員会、1990)
佐賀県教育委員会(1990)『環濠集落 吉野ヶ里遺跡 概報』より
頭のない人骨を埋葬した甕棺、矢じりが刺さったと考えられる人骨などは、何を物語っているのでしょうか。頭のない人骨は、いまでこそ語られることはなくなったと思いますが、かつては奴隷の墓と言われていました。「奴隷」、いいかえるとモノを言う道具といわれるほど、過酷な労働を強いられる階層の人々を指しています。そのような時代があったことは記憶に留めておく必要があります。このような過酷なまたは熾烈な階層の人々のために、製作に数日を要する甕棺を作ることや集落に共住する人々と同列の墓に埋葬されていることを考えると疑問が生じます。これは、何かの出来事に巻き込まれた親族の墓ではないかと想像できます。何かの出来事、そう、争いが容易に想像できます。ムラとムラの間で水争いや耕作地を巡る争いによって戦が起き、戦いの中で、首を切られてしまった仲間の墓だと想像できます。
このように、遺跡の発掘調査で明らかになることは、宝もの探しではなく、人々が生きてきた証を記録し、その時代に何が起こったのか、どのような社会だったのかを考える「証拠」を掴むため、無造作に掘り散らかすのではなく、一つひとつを丁寧に掘り、骨に刺さった小さな矢じり等、遺跡(埋蔵文化財)の記録保存のための発掘調査が行われているのです。
※竪穴住居の発明は、人々の行動範囲を広げ、土器の発明は食材の幅を広げ、幼子、病人、高齢者の食の幅を広げることに大きな貢献をします。稲などの穀物栽培は定住化を促進し、食の安定化と多世代の移住に要する労力を軽減します。
一方、穀物栽培に伴う定住化については、穀物栽培のための時間、ゴミや排泄物処理のための時間など、人々が従来持っていた自由な「時間」を拘束したという考えもあります。どちらが人類にとっていいことなのかは、その後の社会発展の状況から複合的に考えていかなければならないことです。「いいこと」もあれば、「悪いこと」もある。これらを、私たちを取り巻く社会の思想的な背景があり完全とはいえませんが、可能な限り恣意性を排除して観察し、未来に生かしていくことが歴史を学ぶ目的の一つなのです。
2019年06月29日
■創作劇『こころつないで』を、ふか~く楽しむために
■創作劇『こころつないで』を、ふか~く楽しむために(その12)
この「白村江の戦い(百済の役)」敗走と外敵襲来の報は、誰しも疑うことなく次の一歩へむけて突き進むに足る切迫感をもって、我が国の豪族たちの中を駆け巡ったことでしょう。すぐさま、我が国は、筑紫の国に最前線基地である筑紫大宰を守護する水城・大野城・基肄城を築きます。そして、都までの各所に城を築き、各地に烽火(とぶひ のろし場)を置いていきます。
築城ならびに各施設の造営人員は、各地の豪族たちの民が駆り出され従事していきます。これまで同盟関係では成し得なかった「国家」規模での大事業だったのです。

●人夫⑤「まてよ、こりゃ、なにか裏があるな~」
人夫④「この城を造って、この辺りの豪族たちをだまらせようって魂胆だ!」【第2回公演】

●大宰府防衛線(基肄城-大野城-水城)
まさに、大帝国唐と新羅が攻めてくるということを「外装(装い)」しつつ、地域支配のための大和王権の拠点造りに成功するのです。いわばハード整備に成功します。残るは、地域の豪族たちに大王家を支えるという精神的な面、カリスマ性を大王家が帯びること、このことを成し遂げることが、二人の兄弟が描いた古代国家形成へのシナリオに残されるだけとなったのです。
残されたシナリオのはじまりは、くしくも兄の中大兄、天智天皇が我が子大友皇子への世襲意思によって幕を開けることになります。我が国最初の大乱・壬申の乱へと幕はきっておとされることになったのです・・・・・・・・・・【創作劇『こころつないで』の主題からは外れていくので、またの機会に・・・!】
※唐は、天智3年(664)に百済鎮将劉仁願の使者が、翌年も唐の皇帝の使者が続けて来日、新羅は、天智7年(668)に使者が来日しています。唐は新羅を討つための派兵要請であったと伝えられ、新羅は対唐戦争への対処として和親のための使いを倭国へ遣わしていたのです。それなのに、防衛施設を造り続けた理由、それが「基肄城に秘められた思い」の一つだったのです。
※「乱」「変」「役」「戦争」の4つの用語が、戦を標記するとき用いられます。
「乱」は、首謀者が失敗した時(壬申の乱 首謀者は大友皇子で叔父である大海人皇子【後の天武天皇】を討ちに出ます。)
「変」は、首謀者が成功した時(本能寺の変 首謀者は明智光秀で主君織田信長を討ちます。)
「役」は、戦に使役される役目を表現(百済の役、佐賀の役)
「戦争」は、戦を第三者的に表現する時(西南戦争、佐賀戦争)
この「白村江の戦い(百済の役)」敗走と外敵襲来の報は、誰しも疑うことなく次の一歩へむけて突き進むに足る切迫感をもって、我が国の豪族たちの中を駆け巡ったことでしょう。すぐさま、我が国は、筑紫の国に最前線基地である筑紫大宰を守護する水城・大野城・基肄城を築きます。そして、都までの各所に城を築き、各地に烽火(とぶひ のろし場)を置いていきます。
築城ならびに各施設の造営人員は、各地の豪族たちの民が駆り出され従事していきます。これまで同盟関係では成し得なかった「国家」規模での大事業だったのです。

●人夫⑤「まてよ、こりゃ、なにか裏があるな~」
人夫④「この城を造って、この辺りの豪族たちをだまらせようって魂胆だ!」【第2回公演】

●大宰府防衛線(基肄城-大野城-水城)
まさに、大帝国唐と新羅が攻めてくるということを「外装(装い)」しつつ、地域支配のための大和王権の拠点造りに成功するのです。いわばハード整備に成功します。残るは、地域の豪族たちに大王家を支えるという精神的な面、カリスマ性を大王家が帯びること、このことを成し遂げることが、二人の兄弟が描いた古代国家形成へのシナリオに残されるだけとなったのです。
残されたシナリオのはじまりは、くしくも兄の中大兄、天智天皇が我が子大友皇子への世襲意思によって幕を開けることになります。我が国最初の大乱・壬申の乱へと幕はきっておとされることになったのです・・・・・・・・・・【創作劇『こころつないで』の主題からは外れていくので、またの機会に・・・!】
※唐は、天智3年(664)に百済鎮将劉仁願の使者が、翌年も唐の皇帝の使者が続けて来日、新羅は、天智7年(668)に使者が来日しています。唐は新羅を討つための派兵要請であったと伝えられ、新羅は対唐戦争への対処として和親のための使いを倭国へ遣わしていたのです。それなのに、防衛施設を造り続けた理由、それが「基肄城に秘められた思い」の一つだったのです。
※「乱」「変」「役」「戦争」の4つの用語が、戦を標記するとき用いられます。
「乱」は、首謀者が失敗した時(壬申の乱 首謀者は大友皇子で叔父である大海人皇子【後の天武天皇】を討ちに出ます。)
「変」は、首謀者が成功した時(本能寺の変 首謀者は明智光秀で主君織田信長を討ちます。)
「役」は、戦に使役される役目を表現(百済の役、佐賀の役)
「戦争」は、戦を第三者的に表現する時(西南戦争、佐賀戦争)
2019年06月27日
■創作劇『こころつないで』を、ふか~く楽しむために
■創作劇『こころつないで』を、ふか~く楽しむために(その11)
金春秋の敷いたレールの上を中大兄と大海人の兄弟は走って行きます。しかし、勝っても負けても、二人の兄弟は、自らの利にする。用意周到な戦略を敷き、豪族同盟倭軍は「百済の役」へ出撃していきます。前将軍、中将軍、後将軍と縦列隊列を組み、百済救済のため韓半島を目指していくのです。中大兄、大海人は出征しません。そのような中、彼らの母であり天皇であった斎明が筑紫の地で亡くなります。外征の地での崩御でした。軍制トップの崩御であり、軍隊の動揺が想像できますが、動揺を伝える記事は『日本書紀』に見ることはできません。実権者である中大兄の存在とともに、各軍の統制者が各豪族の長であったことが、いわば私兵であったことが功を奏したのかもしれません。いずれにしても、その後の為政権を称制として中大兄が握り、政ごとを司っていきます。
天智二年(663)8月27日・28日、その時がやってきます。
『日本書紀』には「大唐の軍将、戦船一百七十艘を率て、白村江に陣烈れり。戊申に、日本の船師の初づ至る者と、大唐の船師と合ひ戦ふ。日本不利けて退く。・・・・大唐、便ち左右より船挟みて繞み戦ふ。須臾之際に、官軍敗続れぬ。水に赴きて溺れ死ぬる者衆し。・・・・是の時に、百済の王豊璋、数人と船に乗りて、高麗へ逃げ去りぬ。」と記されています。一方、『唐書』劉仁軌伝には「仁軌遇倭兵於白江之口、四戦捷、焚其舟四百艘。煙燄漲天、海水皆赤。・・・」と記されています。主戦場となった白村江、白江は倭・百済の兵士たちの血で真っ赤に染まったと伝えています。

●白村江の戦いの場面【第3回公演】
我が国倭にとって、白村江の大敗です。その敗因は、これまで記してきたように様々な要因が絡み合い、負の方向へと導引されていったのです。しかし、そのことを予想していた中大兄と大海人の二人の兄弟は、すぐさま「負けた時の対処」へと舵を切ります。
「大帝国唐と新羅が海を超えて我が国倭へ攻めてくる。」
・・・・・・・【つづく】
金春秋の敷いたレールの上を中大兄と大海人の兄弟は走って行きます。しかし、勝っても負けても、二人の兄弟は、自らの利にする。用意周到な戦略を敷き、豪族同盟倭軍は「百済の役」へ出撃していきます。前将軍、中将軍、後将軍と縦列隊列を組み、百済救済のため韓半島を目指していくのです。中大兄、大海人は出征しません。そのような中、彼らの母であり天皇であった斎明が筑紫の地で亡くなります。外征の地での崩御でした。軍制トップの崩御であり、軍隊の動揺が想像できますが、動揺を伝える記事は『日本書紀』に見ることはできません。実権者である中大兄の存在とともに、各軍の統制者が各豪族の長であったことが、いわば私兵であったことが功を奏したのかもしれません。いずれにしても、その後の為政権を称制として中大兄が握り、政ごとを司っていきます。
天智二年(663)8月27日・28日、その時がやってきます。
『日本書紀』には「大唐の軍将、戦船一百七十艘を率て、白村江に陣烈れり。戊申に、日本の船師の初づ至る者と、大唐の船師と合ひ戦ふ。日本不利けて退く。・・・・大唐、便ち左右より船挟みて繞み戦ふ。須臾之際に、官軍敗続れぬ。水に赴きて溺れ死ぬる者衆し。・・・・是の時に、百済の王豊璋、数人と船に乗りて、高麗へ逃げ去りぬ。」と記されています。一方、『唐書』劉仁軌伝には「仁軌遇倭兵於白江之口、四戦捷、焚其舟四百艘。煙燄漲天、海水皆赤。・・・」と記されています。主戦場となった白村江、白江は倭・百済の兵士たちの血で真っ赤に染まったと伝えています。

●白村江の戦いの場面【第3回公演】
我が国倭にとって、白村江の大敗です。その敗因は、これまで記してきたように様々な要因が絡み合い、負の方向へと導引されていったのです。しかし、そのことを予想していた中大兄と大海人の二人の兄弟は、すぐさま「負けた時の対処」へと舵を切ります。
「大帝国唐と新羅が海を超えて我が国倭へ攻めてくる。」
・・・・・・・【つづく】
2019年06月26日
■創作劇『こころつないで』を、ふか~く楽しむために
■創作劇『こころつないで』を、ふか~く楽しむために(その10)
6.人夫④のセリフに込められた「基肄城に秘められたおもい」
厩戸皇子(聖徳太子)の思いを引き継ぎ、氏族制度的社会を脱し、大帝国唐の持つ国家制度的社会を打ち立てなければ、いつかは大陸諸国の属国になるという不安を払しょくすることができない。この危機感の中、中大兄皇子と大海人皇子兄弟は動き始めます。まずは、大化改新として教科書では知られる「乙巳(いっし)の変」で、大王家と肩を並べ台頭してきた蘇我本宗家を打倒し、大王家の手に為政権を取り戻します。その後、大化2年(646)、改新の詔で古代国家の基盤となる諸制度を提起しますが、やはり厩戸皇子の前に立ちはだかった巨大な壁が二人の兄弟の前に立ちはだかります。「どうにかしなければ、大帝国唐のような中央集権的国家制度は導入できない。」と思い悩みます。
と、その時、百済救済のための海外遠征である「百済の役」が二人の兄弟の前に背負わされたのです。その時、二人の兄弟の脳裏に、外征には、二つの働きが思い浮かびます。勝てば、カリスマ性が大王家に備わり、負ければ、外敵を想定し一致団結した結束感が生まれます。どちらに転んでも、国家への道を歩むには利用できる手段が転がり込んできたと思ったに違いありません。
まずは、地方の豪族たちに大王の姿を見せ、大王家本体が外征する意気込みと万が一大帝国唐に勝った時のカリスマ性を帯びる象徴としての大王を豪族たちの意識に刷り込むと同時に、豪族の私兵を集め、「クニ」を守るための同盟軍を結成していきます。

●白村江の戦いへの道のり
武光 誠他監修(2012)『地図・年表・図解でみる日本の歴史(上)』より抽出改変
しかし二人の兄弟の中には、同盟軍では大帝国唐の国家軍には太刀打ちできないことは容易に想像できていたのかもしれません。ここにも、二人の兄弟の戦略を見ることができます。そして、宮を「地つきる地」である「つくし(筑紫)」の地に築き、最前線基地として百済の役に臨むことを実行に移していきます。
・・・・・・・・・【つづく】
6.人夫④のセリフに込められた「基肄城に秘められたおもい」
厩戸皇子(聖徳太子)の思いを引き継ぎ、氏族制度的社会を脱し、大帝国唐の持つ国家制度的社会を打ち立てなければ、いつかは大陸諸国の属国になるという不安を払しょくすることができない。この危機感の中、中大兄皇子と大海人皇子兄弟は動き始めます。まずは、大化改新として教科書では知られる「乙巳(いっし)の変」で、大王家と肩を並べ台頭してきた蘇我本宗家を打倒し、大王家の手に為政権を取り戻します。その後、大化2年(646)、改新の詔で古代国家の基盤となる諸制度を提起しますが、やはり厩戸皇子の前に立ちはだかった巨大な壁が二人の兄弟の前に立ちはだかります。「どうにかしなければ、大帝国唐のような中央集権的国家制度は導入できない。」と思い悩みます。
と、その時、百済救済のための海外遠征である「百済の役」が二人の兄弟の前に背負わされたのです。その時、二人の兄弟の脳裏に、外征には、二つの働きが思い浮かびます。勝てば、カリスマ性が大王家に備わり、負ければ、外敵を想定し一致団結した結束感が生まれます。どちらに転んでも、国家への道を歩むには利用できる手段が転がり込んできたと思ったに違いありません。
まずは、地方の豪族たちに大王の姿を見せ、大王家本体が外征する意気込みと万が一大帝国唐に勝った時のカリスマ性を帯びる象徴としての大王を豪族たちの意識に刷り込むと同時に、豪族の私兵を集め、「クニ」を守るための同盟軍を結成していきます。

●白村江の戦いへの道のり
武光 誠他監修(2012)『地図・年表・図解でみる日本の歴史(上)』より抽出改変
しかし二人の兄弟の中には、同盟軍では大帝国唐の国家軍には太刀打ちできないことは容易に想像できていたのかもしれません。ここにも、二人の兄弟の戦略を見ることができます。そして、宮を「地つきる地」である「つくし(筑紫)」の地に築き、最前線基地として百済の役に臨むことを実行に移していきます。
・・・・・・・・・【つづく】
2019年06月25日
■創作劇『こころつないで』を、ふか~く楽しむために
■創作劇『こころつないで』を、ふか~く楽しむために(その9)
5.国家を夢見た聖徳太子の意志とそれを引き継いだ二人の兄弟
国家機構とは、どのような仕組みを持ったものでしょう。国家機構とは単純化できるものではありませんが、様々な価値観を有する人々を一括統制するための制度で、法と法の番人としての警察制度、そして自ら生産行為を行わない階層を支えるための徴税制度を持ち、これらを監理するための官僚機構を機能させる仕組み等が国家制度といわれ、年齢や血縁、地縁で階層を形成し、支配-被支配関係を取り結ぶ氏族制度的な関係から一歩進んだ社会制度と考えられています。
例えば、子どもの頃から共住し先輩-後輩の関係性が明らかな社会と、広域の人々を取りまとめ、先輩か後輩か判然としない社会の二者を考えた時、前者が氏族的社会で後者がその枠を越えた社会と言えます。その枠を越えた時の統括制度として機能するのが国家制度といえます。
枠を越えた広域支配を目指した際に登場したものとして、時を刻み、役所への登庁・退庁の時間を統制する時計制度や、衣服の色によって在位する階級を表現する制度、そして居住する面積を一目で比較し居住者の階級を表現するために四角形の土地区割りを用いる条坊制度、さらには、食膳に並ぶ料理数で階級の上下を表現する食器制度などがあり、その多くは、飛鳥時代末期の天智天皇から天武天皇、そして持統天皇の在位期間の中で制度化されていきます。言い換えると中大兄皇子の時代から始まっていたのです。

●位階と宅地と色分けされた衣服
【奈良文化財研究所(1989)『平城京展』より抽出】

●漏刻(唐代)【奈良文化財研究所(2002)『飛鳥・藤原京展』より抽出】
ただし、国家機構を制度化したのは中大兄皇子-大海人皇子、そして鸕野讃良皇女(うのさららのひめみこ 後の持統天皇)ですが、導入を画策した人物は、聖徳太子として広く知られる厩戸皇子でした。
氏族的社会から脱し、中央集権的な国家機構成立を図るため冠位十二階の制度や十七条憲法を導入しました。しかし、制度は整えても、それに従う人々の意識の中に制度を支える気持ちがなければ、制度を維持していくことはできません。厩戸皇子の「国家」制度導入の試みが広がりをみせなかったのは、そのことを裏付けています。
同じく、中大兄皇子、大海人皇子の兄弟の前にも巨大な障壁が立ちはだかります。

●百済遺民と話し合う中大兄皇子たち【第3回公演】
それは、豪族たちが代々受け継いできた既得権益だったのです。ここをどう打ち破るのかが、氏族制度的社会から国家制度的社会へ飛躍するための巨大なハードル(壁)だったのです。
・・・・・・【つづく】
※新元号「令和」発表後に広く知られることになった梅花の宴を表現したジオラマが、大宰府展示館にあります。その中で官人が色とりどりの服を着ています。これは、多彩な色の服を着ることができたことの表現ではなく、着ている人々の位階を一目で分かるように表現した結果であることを知っていてください。
濃い紫(深紫)が最高位である一位、淡い紫(浅紫)が三位までの貴族、次が赤で四位まで、次に橙色で五位、そして濃い緑で六位、淡い緑色で七位、濃い青で八位、そして色がある最も下位が淡い青で初位があたります。全く色がない白は、位もない無位の者と当時の法令である令に規定されています。

●とびうめ国体採火式での衣装【於:大宰府政庁跡 平成2年(1990)】
※「時計」は、大変失礼ながら沖縄の方々の時間観念が、各種番組で取り上げられており地域ごとの時間の観念があることは知られているところです。一方、様々な時間観念を混在させる国家機構の中では、登庁者がまちまちに登庁されては業務が滞ることも予想されます。このことを統制するための装置として「時計」が登場し、時の記念日のところでも解説しましたが、日本に時計である漏刻を持ち込んだ方が、まさに倭国に国家機構を持ち込もうと画策した中大兄皇子であり天智天皇であったのです。
5.国家を夢見た聖徳太子の意志とそれを引き継いだ二人の兄弟
国家機構とは、どのような仕組みを持ったものでしょう。国家機構とは単純化できるものではありませんが、様々な価値観を有する人々を一括統制するための制度で、法と法の番人としての警察制度、そして自ら生産行為を行わない階層を支えるための徴税制度を持ち、これらを監理するための官僚機構を機能させる仕組み等が国家制度といわれ、年齢や血縁、地縁で階層を形成し、支配-被支配関係を取り結ぶ氏族制度的な関係から一歩進んだ社会制度と考えられています。
例えば、子どもの頃から共住し先輩-後輩の関係性が明らかな社会と、広域の人々を取りまとめ、先輩か後輩か判然としない社会の二者を考えた時、前者が氏族的社会で後者がその枠を越えた社会と言えます。その枠を越えた時の統括制度として機能するのが国家制度といえます。
枠を越えた広域支配を目指した際に登場したものとして、時を刻み、役所への登庁・退庁の時間を統制する時計制度や、衣服の色によって在位する階級を表現する制度、そして居住する面積を一目で比較し居住者の階級を表現するために四角形の土地区割りを用いる条坊制度、さらには、食膳に並ぶ料理数で階級の上下を表現する食器制度などがあり、その多くは、飛鳥時代末期の天智天皇から天武天皇、そして持統天皇の在位期間の中で制度化されていきます。言い換えると中大兄皇子の時代から始まっていたのです。

●位階と宅地と色分けされた衣服
【奈良文化財研究所(1989)『平城京展』より抽出】

●漏刻(唐代)【奈良文化財研究所(2002)『飛鳥・藤原京展』より抽出】
ただし、国家機構を制度化したのは中大兄皇子-大海人皇子、そして鸕野讃良皇女(うのさららのひめみこ 後の持統天皇)ですが、導入を画策した人物は、聖徳太子として広く知られる厩戸皇子でした。
氏族的社会から脱し、中央集権的な国家機構成立を図るため冠位十二階の制度や十七条憲法を導入しました。しかし、制度は整えても、それに従う人々の意識の中に制度を支える気持ちがなければ、制度を維持していくことはできません。厩戸皇子の「国家」制度導入の試みが広がりをみせなかったのは、そのことを裏付けています。
同じく、中大兄皇子、大海人皇子の兄弟の前にも巨大な障壁が立ちはだかります。

●百済遺民と話し合う中大兄皇子たち【第3回公演】
それは、豪族たちが代々受け継いできた既得権益だったのです。ここをどう打ち破るのかが、氏族制度的社会から国家制度的社会へ飛躍するための巨大なハードル(壁)だったのです。
・・・・・・【つづく】
※新元号「令和」発表後に広く知られることになった梅花の宴を表現したジオラマが、大宰府展示館にあります。その中で官人が色とりどりの服を着ています。これは、多彩な色の服を着ることができたことの表現ではなく、着ている人々の位階を一目で分かるように表現した結果であることを知っていてください。
濃い紫(深紫)が最高位である一位、淡い紫(浅紫)が三位までの貴族、次が赤で四位まで、次に橙色で五位、そして濃い緑で六位、淡い緑色で七位、濃い青で八位、そして色がある最も下位が淡い青で初位があたります。全く色がない白は、位もない無位の者と当時の法令である令に規定されています。

●とびうめ国体採火式での衣装【於:大宰府政庁跡 平成2年(1990)】
※「時計」は、大変失礼ながら沖縄の方々の時間観念が、各種番組で取り上げられており地域ごとの時間の観念があることは知られているところです。一方、様々な時間観念を混在させる国家機構の中では、登庁者がまちまちに登庁されては業務が滞ることも予想されます。このことを統制するための装置として「時計」が登場し、時の記念日のところでも解説しましたが、日本に時計である漏刻を持ち込んだ方が、まさに倭国に国家機構を持ち込もうと画策した中大兄皇子であり天智天皇であったのです。
2019年06月23日
■創作劇『こころつないで』を、ふか~く楽しむために
■創作劇『こころつないで』を、ふか~く楽しむために(その8)
4.国家力と同盟力の差を見せつけられた白村江の戦い
天智2年(663)に激突した白村江の戦いは、海の干満差を敗因として倭国と百済の兵士の多くが戦死しました。敗因は海の干満差に多くを帰することに間違いはありませんが、その他に軍団編成、命令系統、基本的な軍備体制など多くの点で、唐軍と韓半島諸国軍ならびに倭軍に大きな差があったと言われています。

●白村江の戦い【第3回公演】
大きな差は、巨石に近い一枚岩軍団であった唐軍と小石の寄せ集め軍団であった百済・倭軍の差異に求められ、徴兵制によって支配圏内から人々を集約し、かつ軍制による一括統制を敷く、いわば国家的な軍団をぶつけてきた唐軍と、各豪族たちの規律で統制された軍団を、盟主である大和大王族の命令を豪族が一旦受けとめ、可否を選択した後攻めに転じるという私兵の寄せ集め的軍団の差であったといわれています。
さらに、軍備についても軍団構成の全てが物語るように、国家的な制度の下で編成された国内の優秀な技術を用いて生産工房群で一括生産された軍備と、各豪族の持つ生産工房で各々の特徴を有する軍備、いわば「斑」のある軍備を持ち戦うことの優劣は、自ずと想像できます。
これら全てを表現したイメージで、国家軍団 唐軍vs同盟軍団 倭国軍の差を周到に表現した図が、下記書籍に描かれています。機会があれば御覧ください。
●白村江の戦い(『週間 新発見!日本の歴史10 飛鳥時代2』に掲載)
この敗因を、起こり得るべくして起こった、必然だと認識していた二人の兄弟がいました。
そう、劇中のキーパーソンの二人である中大兄皇子と大海人皇子の兄弟です。この二人は、国家機構を創り上げることを大王族の先達であった厩戸皇子(聖徳太子)から受け継ぎ、模索していたのです。
・・・・・・【つづく】
4.国家力と同盟力の差を見せつけられた白村江の戦い
天智2年(663)に激突した白村江の戦いは、海の干満差を敗因として倭国と百済の兵士の多くが戦死しました。敗因は海の干満差に多くを帰することに間違いはありませんが、その他に軍団編成、命令系統、基本的な軍備体制など多くの点で、唐軍と韓半島諸国軍ならびに倭軍に大きな差があったと言われています。

●白村江の戦い【第3回公演】
大きな差は、巨石に近い一枚岩軍団であった唐軍と小石の寄せ集め軍団であった百済・倭軍の差異に求められ、徴兵制によって支配圏内から人々を集約し、かつ軍制による一括統制を敷く、いわば国家的な軍団をぶつけてきた唐軍と、各豪族たちの規律で統制された軍団を、盟主である大和大王族の命令を豪族が一旦受けとめ、可否を選択した後攻めに転じるという私兵の寄せ集め的軍団の差であったといわれています。
さらに、軍備についても軍団構成の全てが物語るように、国家的な制度の下で編成された国内の優秀な技術を用いて生産工房群で一括生産された軍備と、各豪族の持つ生産工房で各々の特徴を有する軍備、いわば「斑」のある軍備を持ち戦うことの優劣は、自ずと想像できます。
これら全てを表現したイメージで、国家軍団 唐軍vs同盟軍団 倭国軍の差を周到に表現した図が、下記書籍に描かれています。機会があれば御覧ください。
●白村江の戦い(『週間 新発見!日本の歴史10 飛鳥時代2』に掲載)
この敗因を、起こり得るべくして起こった、必然だと認識していた二人の兄弟がいました。
そう、劇中のキーパーソンの二人である中大兄皇子と大海人皇子の兄弟です。この二人は、国家機構を創り上げることを大王族の先達であった厩戸皇子(聖徳太子)から受け継ぎ、模索していたのです。
・・・・・・【つづく】
2019年06月21日
■創作劇『こころつないで』を、ふか~く楽しむために
■創作劇『こころつないで』を、ふか~く楽しむために(その7)
実は、『日本書紀』孝徳大化三年条に
『日本書紀』孝徳大化三年
「新羅、遣上臣大阿飡金春秋等、送博士小德高向黑麻呂・小山中中臣連押熊、來獻孔雀一隻・鸚鵡一隻。仍以春秋爲質。春秋美姿顏善談笑。造渟足柵、置柵戸。老人等相謂之曰、數年鼠向東行、此造柵之兆乎。」
という記事が見え、金春秋のことが、「春秋美姿顏善談笑(春秋は、容姿美しく、談笑するに善し)。」と記されています。孔雀や鸚鵡とともに「質」として遣わされた金春秋で、それ以上もそれ以下も記されていないため、何を目的に来ていたのかを推し量ることはできませんが、この僅かな記述から見えてくることは、大王家や皇族家に関わらず多くの人々と会話を交わす金春秋の姿が想像されます。
その後の唐への渡航を考慮すると、新羅の切迫した情勢を背負いつつ、倭と組むか、最も避けたいにも関わらず残る唐と組むのかの決断を、この時したのではないかと考えられます。結果として、金春秋の下した結果は、最も避けるべき手段であった韓半島にとって異民族である唐との連合を苦慮しつつ決断したことになります。
唐に傾斜した理由は、二つ。
一つは、倭で見た、倭と百済の結びつきの太さと、百済王義慈なき後は、その子である豊璋の担ぎ出しを見通した上での判断であったこと。そしてもう一つは、新羅が唐の制度を受け入れ親唐派の国であることを見せつけることで、唐の太宗に新羅を認めさせることに成功したことと想像できます。

●唐の太宗へ百済討伐を進言する新羅からの使者【第3回公演】
高句麗討伐に手を焼き、国内情勢も危うくなりつつあった唐にとって、金春秋からの提案は、危機を打開するに不安は残しつつも取り組むに足るという判断を下し、軍隊を動かすことになります。劇中では、金春秋の一連の策略は描かれませんが、新羅からの使者を迎え、唐の太宗が決断する場面として描かれています。

●新羅からの竹簡を読む太宗【第1回公演】
金春秋の長年の願いであった、長く続く韓半島の争いの火を消し、金春秋の死後にその子法敏(後の文武王)によって中国 唐の力を借りつつ三韓統一を成し遂げ、ついには中国 唐の排除に成功し、「統一新羅」として韓半島に住んでいた人々を統括することに成功するのです。この激動の中の一つの出来事として白村江の戦いは歴史の中に登場することになるのです。
この金春秋(太宗武烈)を主人公とした韓国ドラマがあります。韓国KBSテレビ制作の『大王の夢 ~王たちの戦争~』です。金春秋が新羅復興に立ち上がり、高句麗・倭・唐を綱渡り外交を演じつつ、三韓統一を成し遂げる姿を描いたドラマで、倭国の描き方に大きな違和感を禁じ得ませんが、金春秋の心情がよく描かれており、韓国側からみた原始から古代への東アジア情勢を知る上で参考になります。
実は、『日本書紀』孝徳大化三年条に
『日本書紀』孝徳大化三年
「新羅、遣上臣大阿飡金春秋等、送博士小德高向黑麻呂・小山中中臣連押熊、來獻孔雀一隻・鸚鵡一隻。仍以春秋爲質。春秋美姿顏善談笑。造渟足柵、置柵戸。老人等相謂之曰、數年鼠向東行、此造柵之兆乎。」
という記事が見え、金春秋のことが、「春秋美姿顏善談笑(春秋は、容姿美しく、談笑するに善し)。」と記されています。孔雀や鸚鵡とともに「質」として遣わされた金春秋で、それ以上もそれ以下も記されていないため、何を目的に来ていたのかを推し量ることはできませんが、この僅かな記述から見えてくることは、大王家や皇族家に関わらず多くの人々と会話を交わす金春秋の姿が想像されます。
その後の唐への渡航を考慮すると、新羅の切迫した情勢を背負いつつ、倭と組むか、最も避けたいにも関わらず残る唐と組むのかの決断を、この時したのではないかと考えられます。結果として、金春秋の下した結果は、最も避けるべき手段であった韓半島にとって異民族である唐との連合を苦慮しつつ決断したことになります。
唐に傾斜した理由は、二つ。
一つは、倭で見た、倭と百済の結びつきの太さと、百済王義慈なき後は、その子である豊璋の担ぎ出しを見通した上での判断であったこと。そしてもう一つは、新羅が唐の制度を受け入れ親唐派の国であることを見せつけることで、唐の太宗に新羅を認めさせることに成功したことと想像できます。

●唐の太宗へ百済討伐を進言する新羅からの使者【第3回公演】
高句麗討伐に手を焼き、国内情勢も危うくなりつつあった唐にとって、金春秋からの提案は、危機を打開するに不安は残しつつも取り組むに足るという判断を下し、軍隊を動かすことになります。劇中では、金春秋の一連の策略は描かれませんが、新羅からの使者を迎え、唐の太宗が決断する場面として描かれています。

●新羅からの竹簡を読む太宗【第1回公演】
金春秋の長年の願いであった、長く続く韓半島の争いの火を消し、金春秋の死後にその子法敏(後の文武王)によって中国 唐の力を借りつつ三韓統一を成し遂げ、ついには中国 唐の排除に成功し、「統一新羅」として韓半島に住んでいた人々を統括することに成功するのです。この激動の中の一つの出来事として白村江の戦いは歴史の中に登場することになるのです。
この金春秋(太宗武烈)を主人公とした韓国ドラマがあります。韓国KBSテレビ制作の『大王の夢 ~王たちの戦争~』です。金春秋が新羅復興に立ち上がり、高句麗・倭・唐を綱渡り外交を演じつつ、三韓統一を成し遂げる姿を描いたドラマで、倭国の描き方に大きな違和感を禁じ得ませんが、金春秋の心情がよく描かれており、韓国側からみた原始から古代への東アジア情勢を知る上で参考になります。
2019年06月20日
■創作劇『こころつないで』を、ふか~く楽しむために
■創作劇『こころつないで』を、ふか~く楽しむために(その6)
3.策士 金春秋(新羅王太宗・武烈)の狙い
素朴な疑問として、何故、倭国は百済復興軍を組織し、当時、無謀ともいえる大帝国・唐との戦いに突入していったのでしょうか?その鍵を握る人物が、金春秋でした。
金春秋、新羅王族であり後の第29代新羅王で、諡(おくりな)を武烈、号を太宗とする人物です。生まれは定かではありませんが602年頃から661年を生き、新羅王武烈としての在位期間は654年から661年で、百済滅亡の翌年に崩御しています。

●太宗武烈像【金 春秋】
金春秋は、韓族を一つにし、大陸の脅威・唐を排除するために高句麗、倭との和親を取り付ける外交手段に出ています。金春秋の思いは、高句麗と百済は、元来同族でありながら何故争い続けるのか。また韓半島に暮らす人々が何故争い、多くの血を流す必要があるのかという問いに悩みます。そこで、642年に高句麗へ、647年に倭に、そして648年に唐へ自ら出向いた記事が『三国史記』新羅本紀および『日本書紀』に記されています。1370年前、命がけでの航海が当たり前であったこの頃に、7年間の間に3ヶ国を巡り、特に倭から唐へは僅か1年の間に動いているこの状況の裏に何があるのでしょうか?
高句麗と唐への外交交渉は、韓半島で新羅にとって直近の脅威であった対百済対策であったことは想像できます。そして倭への外交は、新羅にとって百済に対して背後に位置する倭の情勢を探るという目的は一つ考えられますが、もう一つの目的が見えてきます。倭に「質(人質)」として17年間滞在していた百済の王族扶余豊璋(余豊璋)の動静と倭との親密度を探ることではなかったかと言われています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【つづく】
3.策士 金春秋(新羅王太宗・武烈)の狙い
素朴な疑問として、何故、倭国は百済復興軍を組織し、当時、無謀ともいえる大帝国・唐との戦いに突入していったのでしょうか?その鍵を握る人物が、金春秋でした。
金春秋、新羅王族であり後の第29代新羅王で、諡(おくりな)を武烈、号を太宗とする人物です。生まれは定かではありませんが602年頃から661年を生き、新羅王武烈としての在位期間は654年から661年で、百済滅亡の翌年に崩御しています。

●太宗武烈像【金 春秋】
金春秋は、韓族を一つにし、大陸の脅威・唐を排除するために高句麗、倭との和親を取り付ける外交手段に出ています。金春秋の思いは、高句麗と百済は、元来同族でありながら何故争い続けるのか。また韓半島に暮らす人々が何故争い、多くの血を流す必要があるのかという問いに悩みます。そこで、642年に高句麗へ、647年に倭に、そして648年に唐へ自ら出向いた記事が『三国史記』新羅本紀および『日本書紀』に記されています。1370年前、命がけでの航海が当たり前であったこの頃に、7年間の間に3ヶ国を巡り、特に倭から唐へは僅か1年の間に動いているこの状況の裏に何があるのでしょうか?
高句麗と唐への外交交渉は、韓半島で新羅にとって直近の脅威であった対百済対策であったことは想像できます。そして倭への外交は、新羅にとって百済に対して背後に位置する倭の情勢を探るという目的は一つ考えられますが、もう一つの目的が見えてきます。倭に「質(人質)」として17年間滞在していた百済の王族扶余豊璋(余豊璋)の動静と倭との親密度を探ることではなかったかと言われています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【つづく】
2019年06月19日
■創作劇『こころつないで』を、ふか~く楽しむために
■創作劇『こころつないで』を、ふか~く楽しむために(その5)
韓半島の中で、最も倭国に情報や文物をもたらしてくれていたのが韓半島西部、中国大陸に近い百済だったのです。ただし、倭国としては韓半島一国に傾注していたわけではなく、韓半島北部の高句麗や東部の新羅との交流も継続はしていました。
しかし、斎明6年(660)年、百済の王義慈の失政により、百済が滅亡します。韓半島統一を目指す新羅と韓半島征服を企てる唐の連合軍に敗れてしまうのです。
義慈王は唐へ送還されてしまいますが、すぐさま、鬼室福信を中心とする百済復興軍が建てられ、その中心に据えられたのが、義慈王の子豊璋だったのです。
この豊璋こそ、倭国が白村江の戦いへと突き進まなければならなかった理由を握る人物でした。
豊璋、こと余豊璋(扶余豊璋)で、劇中では第2場の唐国でのやりとりの中で登場します。余豊璋は、遡ること舒明3年(631)に「百済の王義慈、王子豊璋を入りて質とす」と『日本書紀』は伝えています。ただし、この年は、百済の王は義慈ではないため記述内容の信ぴょう性は疑わしいとされています。その後、余豊璋の名が見えるのは皇極2年(643)に、養蜂に失敗したという内容で『日本書紀』に記されています。
『日本書紀』皇極天皇二年(643)
「是歳、百済の太子余豊(余豊璋)、蜜蜂の房四枚を以て、三輪山に放ち養ふ。而して終に蕃息らず」
この頃には、確実に倭国にいたことは考えられ、この時前後から斎明6年(660)までの17年間を倭国で過ごしていたことになります。この長きにわたり、大和王権の政争渦巻く脇ですごしていた余豊璋、王権を担っていた中大兄や大海人、そして二人の兄弟の母であった斎明天皇に「情」が生まれていなかったとはいえないでしょう。百済滅亡後に、余豊璋を韓半島へ5000人余の軍とともに送り届けていることにも表現されています。
しかし、この状況をそばでつぶさに観察し、百済-倭の連合を画策した人物がいたのです。
そう、その人物こそ、後の新羅王武烈となる金春秋(きむ ちゅんちゅ)、その人だったのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・【つづく】
韓半島の中で、最も倭国に情報や文物をもたらしてくれていたのが韓半島西部、中国大陸に近い百済だったのです。ただし、倭国としては韓半島一国に傾注していたわけではなく、韓半島北部の高句麗や東部の新羅との交流も継続はしていました。
しかし、斎明6年(660)年、百済の王義慈の失政により、百済が滅亡します。韓半島統一を目指す新羅と韓半島征服を企てる唐の連合軍に敗れてしまうのです。
義慈王は唐へ送還されてしまいますが、すぐさま、鬼室福信を中心とする百済復興軍が建てられ、その中心に据えられたのが、義慈王の子豊璋だったのです。
この豊璋こそ、倭国が白村江の戦いへと突き進まなければならなかった理由を握る人物でした。
豊璋、こと余豊璋(扶余豊璋)で、劇中では第2場の唐国でのやりとりの中で登場します。余豊璋は、遡ること舒明3年(631)に「百済の王義慈、王子豊璋を入りて質とす」と『日本書紀』は伝えています。ただし、この年は、百済の王は義慈ではないため記述内容の信ぴょう性は疑わしいとされています。その後、余豊璋の名が見えるのは皇極2年(643)に、養蜂に失敗したという内容で『日本書紀』に記されています。
『日本書紀』皇極天皇二年(643)
「是歳、百済の太子余豊(余豊璋)、蜜蜂の房四枚を以て、三輪山に放ち養ふ。而して終に蕃息らず」
この頃には、確実に倭国にいたことは考えられ、この時前後から斎明6年(660)までの17年間を倭国で過ごしていたことになります。この長きにわたり、大和王権の政争渦巻く脇ですごしていた余豊璋、王権を担っていた中大兄や大海人、そして二人の兄弟の母であった斎明天皇に「情」が生まれていなかったとはいえないでしょう。百済滅亡後に、余豊璋を韓半島へ5000人余の軍とともに送り届けていることにも表現されています。
しかし、この状況をそばでつぶさに観察し、百済-倭の連合を画策した人物がいたのです。
そう、その人物こそ、後の新羅王武烈となる金春秋(きむ ちゅんちゅ)、その人だったのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・【つづく】
2019年06月18日
■創作劇『こころつないで』を、ふか~く楽しむために
■創作劇『こころつないで』を、ふか~く楽しむために(その4)
2.なぜ、白村江へむかわなければならなかったのか
白村江の戦いは、天智2年(西暦663)に起こった百済救済のための戦いで、「百済の役(えだち)」と呼称されています。結果として天智2年8月28日、干潮の時間を見誤った倭・百済の軍船は座礁し、白村江の海は真っ赤に染まったといわれています。
なぜ、白村江の戦いへ、言い替えると韓半島西部にあった一国の百済の救済の戦いへむかわなければならなかったのでしょうか。
そもそも百済という国はどのような国だったのでしょう?
百済の始祖は、実は韓半島北部の国高句麗にあり、元をたどれば中国東北地方にあった扶余の一族でった朱蒙(ちゅもん)が起こした国高句麗にあって、始祖王朱蒙の子であった温祚(おんじょ)が、高句麗の太子との対立を避けて、十人の家臣とともに韓半島南部に行き建てた国が百済の元となる「十済」であったと言われています。時に、紀元前18年、日本では弥生時代中期にあたります。このことに、百済王が「扶余」姓を名のる理由があります。

●5世紀から6世紀ごろの韓半島情勢
(韓半島情勢は、安定的な状況ではなく、図に示した各国の領域も、その時々で大きく変化しています。おおよその地理的な位置として御理解ください。)
話を戻して、日本にとって韓半島の諸国は、大陸の優れた文物や情報を得るために必要な情報源であり、韓半島の諸国を介して、仏教や多くの制度、鉄などの優れた文物を手に入れていました。韓半島諸国も、隋や唐など大陸の脅威に対して、背後に位置する倭とつながることは、退路を確保するとともに、挟み撃ちをさけるためにも重要な課題でした。
・・・・・・【つづく】
2.なぜ、白村江へむかわなければならなかったのか
白村江の戦いは、天智2年(西暦663)に起こった百済救済のための戦いで、「百済の役(えだち)」と呼称されています。結果として天智2年8月28日、干潮の時間を見誤った倭・百済の軍船は座礁し、白村江の海は真っ赤に染まったといわれています。
なぜ、白村江の戦いへ、言い替えると韓半島西部にあった一国の百済の救済の戦いへむかわなければならなかったのでしょうか。
そもそも百済という国はどのような国だったのでしょう?
百済の始祖は、実は韓半島北部の国高句麗にあり、元をたどれば中国東北地方にあった扶余の一族でった朱蒙(ちゅもん)が起こした国高句麗にあって、始祖王朱蒙の子であった温祚(おんじょ)が、高句麗の太子との対立を避けて、十人の家臣とともに韓半島南部に行き建てた国が百済の元となる「十済」であったと言われています。時に、紀元前18年、日本では弥生時代中期にあたります。このことに、百済王が「扶余」姓を名のる理由があります。

●5世紀から6世紀ごろの韓半島情勢
(韓半島情勢は、安定的な状況ではなく、図に示した各国の領域も、その時々で大きく変化しています。おおよその地理的な位置として御理解ください。)
話を戻して、日本にとって韓半島の諸国は、大陸の優れた文物や情報を得るために必要な情報源であり、韓半島の諸国を介して、仏教や多くの制度、鉄などの優れた文物を手に入れていました。韓半島諸国も、隋や唐など大陸の脅威に対して、背後に位置する倭とつながることは、退路を確保するとともに、挟み撃ちをさけるためにも重要な課題でした。
・・・・・・【つづく】
2019年06月17日
■創作劇『こころつないで』を、ふか~く楽しむために
■創作劇『こころつないで』を、ふか~く楽しむために(その3)
そして、もう一つの時代が、「現代」です。
現代を生きる小学生が飛鳥時代へタイムスリップする物語ですが、現代社会の問題も同時に描いています。学力重視社会、いじめ、偏食、男女差別(性差別)、戦争など、私たちを同時代的に取り巻く問題も劇中の随所にちりばめられています。これら社会問題を、小学生たちがタイムスリップし体感していく過程で、自らの歩む道を見つけていきます。暗闇の中であらわれる不思議な少年が、「君たちがこれから、どう生きていきたいかを見つけ出すこと」、そして「見つけるためにここに来たんだ。」と言い放ちます。「やさしく『見守る』」「危ない・危ないを叫ぶ」「転ぶ前に杖をついてやる」おとな・大人・オトナ。教えられることが、守られることが当たり前になってしまった子どもらに、「自分で考えるんだ!」と。

●「見つけるために、ここに来たんだ!」【第4回公演】
奇しくも、今年の東京大学の入学式で上野千鶴子先生が新入生にむけた祝辞に送られた言葉に表現されています。社会は厳しいところだと。それに立ち向かうための「知」を生み出す「知」を磨き身に付ける場が大学なのだと言われました。自らで考え、自らで身を守り、そして自らで切り拓いていく力を育てていく場が学校であり、社会であるはずだった。そのことを、脚本制作者である福永真理子さんは、「現代」社会を取り入れ、単に歴史物語にしなかった理由があるのです。

●台本読み合わせの様子【第3回公演】
これから、創作劇『こころつないで』を深く知っていただくために、いくつかの項目を深く見ていきましょう。
・・・・・・・・・・・・・【つづく】
そして、もう一つの時代が、「現代」です。
現代を生きる小学生が飛鳥時代へタイムスリップする物語ですが、現代社会の問題も同時に描いています。学力重視社会、いじめ、偏食、男女差別(性差別)、戦争など、私たちを同時代的に取り巻く問題も劇中の随所にちりばめられています。これら社会問題を、小学生たちがタイムスリップし体感していく過程で、自らの歩む道を見つけていきます。暗闇の中であらわれる不思議な少年が、「君たちがこれから、どう生きていきたいかを見つけ出すこと」、そして「見つけるためにここに来たんだ。」と言い放ちます。「やさしく『見守る』」「危ない・危ないを叫ぶ」「転ぶ前に杖をついてやる」おとな・大人・オトナ。教えられることが、守られることが当たり前になってしまった子どもらに、「自分で考えるんだ!」と。

●「見つけるために、ここに来たんだ!」【第4回公演】
奇しくも、今年の東京大学の入学式で上野千鶴子先生が新入生にむけた祝辞に送られた言葉に表現されています。社会は厳しいところだと。それに立ち向かうための「知」を生み出す「知」を磨き身に付ける場が大学なのだと言われました。自らで考え、自らで身を守り、そして自らで切り拓いていく力を育てていく場が学校であり、社会であるはずだった。そのことを、脚本制作者である福永真理子さんは、「現代」社会を取り入れ、単に歴史物語にしなかった理由があるのです。

●台本読み合わせの様子【第3回公演】
これから、創作劇『こころつないで』を深く知っていただくために、いくつかの項目を深く見ていきましょう。
・・・・・・・・・・・・・【つづく】
2019年06月16日
■創作劇『こころつないで』を、ふか~く楽しむために
■創作劇『こころつないで』を、ふか~く楽しむために(その2)
国家機構をつくり上げ、大陸諸国と肩をならべる「大国」になるために、大王家の二人の兄弟が動きます。二人の兄弟、そう乙巳の変(教科書的には「大化の改新」)で蘇我本宗家を討伐し、大王家の手に政治の主導権を取り戻した事件を成功させた中大兄皇子とその弟である大海人皇子です。国家機構をつくりさらに定着させるためには、日本初となる大乱・壬申の乱を経る必要がありますが、創作劇中では登場しないものの忘れてはならない人が、大海人皇子の妻であり、後の天皇となった持統天皇も忘れることはできません。兄の志を弟が引き継ぎ、そして夫の志を引き継ぎ、古代国家機構を「安定」に導いた妻・持統天皇の3人の力と知恵、そしてカリスマ性が成し得たことだったのです。

●中大兄皇子の決意!【第4回公演】
もう一人、「基肄城に秘められたおもい」を聴衆に伝える重要な役割を務める人物が、人夫④です。といっても歴史上の人物ではないのですが、白村江の大敗を大義とし、国家存亡の危機を「外装」しつつ防衛施設としての基肄城、大野城、水城を造っていた、その頃、唐、新羅は和親を結ぶべく倭国へ来、その意志を知っていた大王家は、何故、防衛施設を造らせ続けたのか。この疑問を解く鍵を、8年前に『こころつないで』を初演した時から、人夫⑤の「まてよ、こりゃ、なにか裏があるな~」に続いて、人夫④が、「この城を造って、この辺りの豪族たちをだまらせようって魂胆だ!」と言ってくれているのです。

●「なにか裏があるな~っ」【第4回公演】
創作劇『こころつないで』は、基肄城が、白村江の大敗をきっかけとして国土防衛拠点として築かれていったという表面的な物語ではなく、その背後には、東アジア情勢や倭国(大和王権)から日本(大和政権)へと国家形成への道を進む過程を物語る激動の歴史を描いています。だからこそ、その証の一つとして、基肄城跡跡は、国の宝としての特別史跡に指定されているのです。
創作劇『こころつないで』を描く上でのキーパーソンは4人。劇中ではセリフ中にしか登場しない新羅の策士・金春秋、後の太宗武烈王、そしてキャストとして登場する国家機構を築き上げた中大兄皇子、大海人皇子の二人の兄弟、基肄城築城の歴史的背景をさりげなく語る人夫④なのです。・・・・・・【つづく】
国家機構をつくり上げ、大陸諸国と肩をならべる「大国」になるために、大王家の二人の兄弟が動きます。二人の兄弟、そう乙巳の変(教科書的には「大化の改新」)で蘇我本宗家を討伐し、大王家の手に政治の主導権を取り戻した事件を成功させた中大兄皇子とその弟である大海人皇子です。国家機構をつくりさらに定着させるためには、日本初となる大乱・壬申の乱を経る必要がありますが、創作劇中では登場しないものの忘れてはならない人が、大海人皇子の妻であり、後の天皇となった持統天皇も忘れることはできません。兄の志を弟が引き継ぎ、そして夫の志を引き継ぎ、古代国家機構を「安定」に導いた妻・持統天皇の3人の力と知恵、そしてカリスマ性が成し得たことだったのです。

●中大兄皇子の決意!【第4回公演】
もう一人、「基肄城に秘められたおもい」を聴衆に伝える重要な役割を務める人物が、人夫④です。といっても歴史上の人物ではないのですが、白村江の大敗を大義とし、国家存亡の危機を「外装」しつつ防衛施設としての基肄城、大野城、水城を造っていた、その頃、唐、新羅は和親を結ぶべく倭国へ来、その意志を知っていた大王家は、何故、防衛施設を造らせ続けたのか。この疑問を解く鍵を、8年前に『こころつないで』を初演した時から、人夫⑤の「まてよ、こりゃ、なにか裏があるな~」に続いて、人夫④が、「この城を造って、この辺りの豪族たちをだまらせようって魂胆だ!」と言ってくれているのです。

●「なにか裏があるな~っ」【第4回公演】
創作劇『こころつないで』は、基肄城が、白村江の大敗をきっかけとして国土防衛拠点として築かれていったという表面的な物語ではなく、その背後には、東アジア情勢や倭国(大和王権)から日本(大和政権)へと国家形成への道を進む過程を物語る激動の歴史を描いています。だからこそ、その証の一つとして、基肄城跡跡は、国の宝としての特別史跡に指定されているのです。
創作劇『こころつないで』を描く上でのキーパーソンは4人。劇中ではセリフ中にしか登場しない新羅の策士・金春秋、後の太宗武烈王、そしてキャストとして登場する国家機構を築き上げた中大兄皇子、大海人皇子の二人の兄弟、基肄城築城の歴史的背景をさりげなく語る人夫④なのです。・・・・・・【つづく】
2019年06月15日
■創作劇『こころつないで』を、ふか~く楽しむために
■創作劇『こころつないで』を、ふか~く楽しむために(その1)
当会は、きやま創作劇実行委員会の構成団体の一つとして、関係機関と協働してきやま創作劇を支えています。
創作劇『こころつないで -基肄城に秘められたおもい-』を観ていただくにあたり、劇中では深く語られることがない社会や時代背景について、ここで深く記してみましょう。
創作劇『こころつないで』を御覧になる際の、予備知識としてお役立ていただければ幸いです。

●「約束するよ!」【第1回公演】
1.時代背景とキーパーソンの4人
『こころつないで』が描く時代は2つ。特別史跡基肄城跡が造られた飛鳥時代と、そして現代です。
基肄城が造られた飛鳥時代は、その後の奈良時代に古代国家機構を創るための基礎となった時代であり、古墳を築いていた地域の豪族たちとの連合同盟関係によってまとまっていた時代でした。劇中で登場する中大兄皇子や大海人皇子の兄弟、そして彼らの母親である斎明天皇は、大和の「クニ」の豪族連合体の長の一族であり、全国に同盟連合の網を広げていた頃で、「天皇」号はまだ人々に「公認」されていなかった時代だったのです。

●斎明天皇の決意【第1回公演】

●唐の韓半島侵出へ【第4回公演】
一方、韓半島では新羅・百済・高句麗の三国が覇権を争いせめぎ合いを続けています。その韓半島での覇権を奪う大陸勢力が唐だったのです。韓半島三国の中で、弱小国家が新羅で、百済と高句麗から攻められ、風前の灯状態に陥っていたのでした。その中から新羅を韓半島統一、いわば三韓統一まで駆け上らせた金春秋が、新羅の救世主のごとく登場してきたのです。金春秋、この人こそが倭の国と百済を結び付け、白村江の戦いの渦へと引き込んでいった張本人だったのです。 ・・・・・・・・・【つづく】
当会は、きやま創作劇実行委員会の構成団体の一つとして、関係機関と協働してきやま創作劇を支えています。
創作劇『こころつないで -基肄城に秘められたおもい-』を観ていただくにあたり、劇中では深く語られることがない社会や時代背景について、ここで深く記してみましょう。
創作劇『こころつないで』を御覧になる際の、予備知識としてお役立ていただければ幸いです。

●「約束するよ!」【第1回公演】
1.時代背景とキーパーソンの4人
『こころつないで』が描く時代は2つ。特別史跡基肄城跡が造られた飛鳥時代と、そして現代です。
基肄城が造られた飛鳥時代は、その後の奈良時代に古代国家機構を創るための基礎となった時代であり、古墳を築いていた地域の豪族たちとの連合同盟関係によってまとまっていた時代でした。劇中で登場する中大兄皇子や大海人皇子の兄弟、そして彼らの母親である斎明天皇は、大和の「クニ」の豪族連合体の長の一族であり、全国に同盟連合の網を広げていた頃で、「天皇」号はまだ人々に「公認」されていなかった時代だったのです。

●斎明天皇の決意【第1回公演】

●唐の韓半島侵出へ【第4回公演】
一方、韓半島では新羅・百済・高句麗の三国が覇権を争いせめぎ合いを続けています。その韓半島での覇権を奪う大陸勢力が唐だったのです。韓半島三国の中で、弱小国家が新羅で、百済と高句麗から攻められ、風前の灯状態に陥っていたのでした。その中から新羅を韓半島統一、いわば三韓統一まで駆け上らせた金春秋が、新羅の救世主のごとく登場してきたのです。金春秋、この人こそが倭の国と百済を結び付け、白村江の戦いの渦へと引き込んでいった張本人だったのです。 ・・・・・・・・・【つづく】
2019年06月13日
■6月10日(その2)
6月10日は、時の記念日、大正10年では「時の宣伝」日でした。
我が町基山にとっては、もう一つ、記念する行事が行われています。
基山(きざん)山頂に天高くそびえて建つ「天智天皇欽仰之碑」建立の記念すべき日でした。今や我が国の特別史跡に指定されている基肄城跡ですが、史跡指定へむけて久保山善映先生を中心とした町民の皆さんが尽力されていた大正から昭和初期の頃、多くの方々の寄付によって建立されたのです。

●「天智天皇欽仰之碑」現況写真
昭和5年(1930)に肥前史談會が発起人となり、佐賀県知事を総裁とする「天智天皇奉賛銅柱建設會」が組織され、翌年6月10日に起工式が執り行われています。そして発起から3ヶ年の月日を経た昭和8年(1933)6月10日に「天智天皇欽仰之碑」として除幕式が行われたのです。

●除幕式時の写真
その時の写真が、『肥前史談』に載せられており、そこには、誇らしげに立つ小学生の姿も見えます。実は、小学生から大人まで、多くの町民が欽仰碑建立に携わり、ご記憶にある皆さまからは、「麓から砂や石をリュックに入れ背負って運んだ。」とお話を伺うことができます。
この時、同時に建立されたのが、欽仰碑の南側にある展望所ならぬ正式名称「通天洞(避難所)」や、「特別史跡基肄城跡」記念碑の北側にある小高い丘の上に展望所が建てられています。残念なことに小高い丘の上に建てられていた展望所は、老朽化のため解体され基礎部分のみが当時の面影を今に伝えています。

●通天洞現況

●展望所現況

●かつての展望所
何気なく建つ基山(きざん)の文化遺産ですが、多くの町民のご努力によって建立されたモノであることは知っておいてください。
※裏話として、「天智天皇欽仰之碑」は、当初は天智天皇の御姿を銅像として建立する計画だったようです。しかし、天皇の御姿を像にすることはまかりならんという、当時の宮内省のお達しで、今の姿になったのでした。ちなみに、天智天皇の御姿を伝える飛鳥時代から受け継がれる絵は、残されていません・・・・・・・。“!”
我が町基山にとっては、もう一つ、記念する行事が行われています。
基山(きざん)山頂に天高くそびえて建つ「天智天皇欽仰之碑」建立の記念すべき日でした。今や我が国の特別史跡に指定されている基肄城跡ですが、史跡指定へむけて久保山善映先生を中心とした町民の皆さんが尽力されていた大正から昭和初期の頃、多くの方々の寄付によって建立されたのです。

●「天智天皇欽仰之碑」現況写真
昭和5年(1930)に肥前史談會が発起人となり、佐賀県知事を総裁とする「天智天皇奉賛銅柱建設會」が組織され、翌年6月10日に起工式が執り行われています。そして発起から3ヶ年の月日を経た昭和8年(1933)6月10日に「天智天皇欽仰之碑」として除幕式が行われたのです。

●除幕式時の写真
その時の写真が、『肥前史談』に載せられており、そこには、誇らしげに立つ小学生の姿も見えます。実は、小学生から大人まで、多くの町民が欽仰碑建立に携わり、ご記憶にある皆さまからは、「麓から砂や石をリュックに入れ背負って運んだ。」とお話を伺うことができます。
この時、同時に建立されたのが、欽仰碑の南側にある展望所ならぬ正式名称「通天洞(避難所)」や、「特別史跡基肄城跡」記念碑の北側にある小高い丘の上に展望所が建てられています。残念なことに小高い丘の上に建てられていた展望所は、老朽化のため解体され基礎部分のみが当時の面影を今に伝えています。

●通天洞現況

●展望所現況

●かつての展望所
何気なく建つ基山(きざん)の文化遺産ですが、多くの町民のご努力によって建立されたモノであることは知っておいてください。
※裏話として、「天智天皇欽仰之碑」は、当初は天智天皇の御姿を銅像として建立する計画だったようです。しかし、天皇の御姿を像にすることはまかりならんという、当時の宮内省のお達しで、今の姿になったのでした。ちなみに、天智天皇の御姿を伝える飛鳥時代から受け継がれる絵は、残されていません・・・・・・・。“!”
2019年06月11日
■6月10日(その1)
昨日、6月10日は「時の記念日」です。
令和ゆかりの地「太宰府」で、大宰府政庁跡を舞台に「時の記念日」の行事が行われました。

●大宰府政庁跡(正殿)で行われた「時の記念日」の行事の様子

●正殿三石碑に掲げられた「時の記念日」掛け軸
早朝午前6時に政庁跡正殿前に参集し、時の大切さと時の記念日の由来について講話が行われ、参集された方々で、「時の記念日」の歌を歌うという素朴な集まりです。太宰府市民遺産第6号にも認定され、200名を超える方々に参加いただくまでになっています。
このように記すと、「今」始まったかのように思われますが、遡ること98年前、時は大正10年(1921)6月10日に全国で取り組まれた「時の記念日」の行事に始まります。
当時発行された「福岡日日新聞(大正10年6月11)朝刊」に、福岡県筑紫郡の「時の宣伝式」の様子が記されています。そこには、飛鳥時代に国家制度の樹立を模索していた時の天皇である天智天皇が、時間観念の制度化を目的として漏刻を始めたことを説き、その時の施設が大宰府では現在の政庁跡東側にある「ときやま(辰山、築山、月山)」にあったという説明が、郷土史家であった武谷水城氏によって正殿跡で行われたと書かれています。その後、水城尋常小学校で祝賀会が執り行われたとも書かれていました。「時の宣伝式」、今で言う「時の記念日」の始まりの姿を伺い知ることができます。

●正殿と「ときやま」
実は、この「時の宣伝式」は、何も太宰府でだけ行われたのではなく、全国各地を舞台に開催されています。
佐賀県内でも各地で行われ、佐賀市役所では正午の午砲とともに「鶏飯」を食べたと記されています。
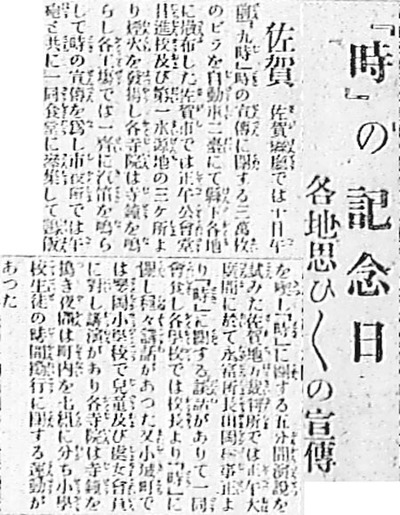
●福岡日日新聞 大正10年6月11日朝刊記事を抽出改変
「時」の観念は、地域によって様々でした。それを統一し国家機構の仕組みとして立ち上げたのが、創作劇「こころつないで」のキーパーソンの一人である中大兄皇子、後の天智天皇であったことは知っておいてください。
令和ゆかりの地「太宰府」で、大宰府政庁跡を舞台に「時の記念日」の行事が行われました。

●大宰府政庁跡(正殿)で行われた「時の記念日」の行事の様子

●正殿三石碑に掲げられた「時の記念日」掛け軸
早朝午前6時に政庁跡正殿前に参集し、時の大切さと時の記念日の由来について講話が行われ、参集された方々で、「時の記念日」の歌を歌うという素朴な集まりです。太宰府市民遺産第6号にも認定され、200名を超える方々に参加いただくまでになっています。
このように記すと、「今」始まったかのように思われますが、遡ること98年前、時は大正10年(1921)6月10日に全国で取り組まれた「時の記念日」の行事に始まります。
当時発行された「福岡日日新聞(大正10年6月11)朝刊」に、福岡県筑紫郡の「時の宣伝式」の様子が記されています。そこには、飛鳥時代に国家制度の樹立を模索していた時の天皇である天智天皇が、時間観念の制度化を目的として漏刻を始めたことを説き、その時の施設が大宰府では現在の政庁跡東側にある「ときやま(辰山、築山、月山)」にあったという説明が、郷土史家であった武谷水城氏によって正殿跡で行われたと書かれています。その後、水城尋常小学校で祝賀会が執り行われたとも書かれていました。「時の宣伝式」、今で言う「時の記念日」の始まりの姿を伺い知ることができます。

●正殿と「ときやま」
実は、この「時の宣伝式」は、何も太宰府でだけ行われたのではなく、全国各地を舞台に開催されています。
佐賀県内でも各地で行われ、佐賀市役所では正午の午砲とともに「鶏飯」を食べたと記されています。
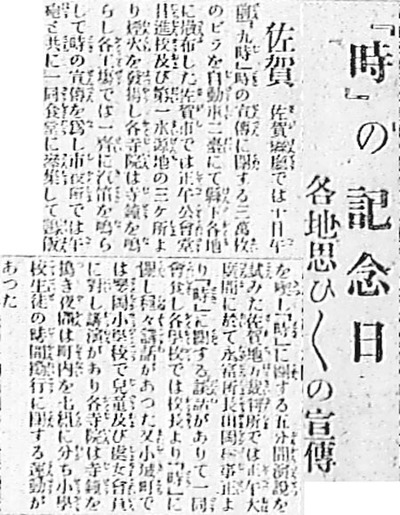
●福岡日日新聞 大正10年6月11日朝刊記事を抽出改変
「時」の観念は、地域によって様々でした。それを統一し国家機構の仕組みとして立ち上げたのが、創作劇「こころつないで」のキーパーソンの一人である中大兄皇子、後の天智天皇であったことは知っておいてください。
2019年06月02日
■町内の文化遺産を清掃!
本日は、県下一斉美化活動で、朝から町内で清掃活動が行われました。
当会会員も参画している基肄かたろう会のメンバーは、住んでいる行政区内の一斉清掃に参加した後、午前10時に町内二ヶ所に分かれ、文化遺産清掃・手入れ作業を行いました。
一ヶ所は、特別史跡基肄城跡(草スキー場側駐車場)の解説板で、もう一ヶ所は枯れ松二国境で清掃活動を行っています。
特別史跡基肄城跡では、風雨のさらされ汚れた特別史跡基城跡の説明板と、今、話題の新元号「令和」の立役者・大伴旅人が基山(きざん)に登り詠んだ「橘の・・・」の万葉歌が記されている解説板を綺麗に清掃しました。

■清掃活動の様子
一方、筑紫野市との市町境であり、佐賀県と福岡県の県境でもある枯れ松二国境のむかし話が伝えられている二国境碑および周辺を、草刈りから石碑・説明板の清掃と手入れを行いました。雑草がのびつつあった二国境整備公園が、会員諸氏の手作業によって見違えるように綺麗になりました。

■清掃前の二国境整備公園

■清掃活動の様子

■綺麗になった二国境整備公園
文化遺産清掃活動は、我が町基山の住民をはじめ、訪れていただく多くの方々が、気持ちよく我が町の文化遺産に接していただくことを目的として、会員諸氏から出た発意で実現しました。

■特別史跡基肄城跡班の面々

■枯れ松二国境班の面々
【各々の班の撮影者が加わり総勢13名で行いました!】
本日、活動に参加された皆さま、お疲れさまでした。
ひと風呂浴びて汗を流し、本日の活動の疲れを「癒して」ください・・・・・・・・。
くれぐれも、「反省」の数だけ杯が積み重なりませんように・・・・・・・・・・・・・・・・・。
当会会員も参画している基肄かたろう会のメンバーは、住んでいる行政区内の一斉清掃に参加した後、午前10時に町内二ヶ所に分かれ、文化遺産清掃・手入れ作業を行いました。
一ヶ所は、特別史跡基肄城跡(草スキー場側駐車場)の解説板で、もう一ヶ所は枯れ松二国境で清掃活動を行っています。
特別史跡基肄城跡では、風雨のさらされ汚れた特別史跡基城跡の説明板と、今、話題の新元号「令和」の立役者・大伴旅人が基山(きざん)に登り詠んだ「橘の・・・」の万葉歌が記されている解説板を綺麗に清掃しました。

■清掃活動の様子
一方、筑紫野市との市町境であり、佐賀県と福岡県の県境でもある枯れ松二国境のむかし話が伝えられている二国境碑および周辺を、草刈りから石碑・説明板の清掃と手入れを行いました。雑草がのびつつあった二国境整備公園が、会員諸氏の手作業によって見違えるように綺麗になりました。

■清掃前の二国境整備公園

■清掃活動の様子

■綺麗になった二国境整備公園
文化遺産清掃活動は、我が町基山の住民をはじめ、訪れていただく多くの方々が、気持ちよく我が町の文化遺産に接していただくことを目的として、会員諸氏から出た発意で実現しました。

■特別史跡基肄城跡班の面々

■枯れ松二国境班の面々
【各々の班の撮影者が加わり総勢13名で行いました!】
本日、活動に参加された皆さま、お疲れさまでした。
ひと風呂浴びて汗を流し、本日の活動の疲れを「癒して」ください・・・・・・・・。
くれぐれも、「反省」の数だけ杯が積み重なりませんように・・・・・・・・・・・・・・・・・。




