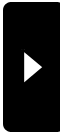2025年04月08日
■オキナグサが咲いてます!
基山(キザン)にも春というより初夏のすがすがしさが似合う季節がやってきました。山頂の植物保護区域にも、オキナグサが「頭を垂れた」お花が咲いています。

【R07.4.8撮影】
オキナグサのお花を目当てに基山(キザン)へ登って来られる方々も、たくさんお見かけするようになりました。
今年は、桜とオキナグサが咲く基山(キザン)、ハイキングにお越しください。
【注意】
絶滅危惧種Ⅱ類(絶滅の危険が増大している種)としてオキナグサは知られていますが、基山(キザン)にしかない固有の植物(天然記念物)ではありません。
未だ保護区域以外に「過剰な保護」を表現する「くし刺し」が後を絶ちません。


【「くし刺し」】 【「くし刺し」除去後】
小さなちびっ子たちも、自然に親しむため沢山登ってきています。
 【基山(キザン)に登る子どもたち】
【基山(キザン)に登る子どもたち】
転んでケガをする元凶にもなりかねません。基山町の環境部署であるまちづくり課と史跡保護の部署である教育学習課が、注意喚起ポスターを掲示しています。

【頂上休憩所に掲示された注意喚起ポスター】
無責任な「過剰な保護」行為は止めて欲しいものです。

【R07.4.8撮影】
オキナグサのお花を目当てに基山(キザン)へ登って来られる方々も、たくさんお見かけするようになりました。
今年は、桜とオキナグサが咲く基山(キザン)、ハイキングにお越しください。
【注意】
絶滅危惧種Ⅱ類(絶滅の危険が増大している種)としてオキナグサは知られていますが、基山(キザン)にしかない固有の植物(天然記念物)ではありません。
未だ保護区域以外に「過剰な保護」を表現する「くし刺し」が後を絶ちません。


【「くし刺し」】 【「くし刺し」除去後】
小さなちびっ子たちも、自然に親しむため沢山登ってきています。
 【基山(キザン)に登る子どもたち】
【基山(キザン)に登る子どもたち】転んでケガをする元凶にもなりかねません。基山町の環境部署であるまちづくり課と史跡保護の部署である教育学習課が、注意喚起ポスターを掲示しています。

【頂上休憩所に掲示された注意喚起ポスター】
無責任な「過剰な保護」行為は止めて欲しいものです。
2025年03月25日
■令和6年度基肄城関連事業終了
令和6年度に基山町から受託した特別史跡基肄城跡ほか町内遺跡周知活用事業が、令和7年3月23日をもって終了いたしました。受託した内容は、①特別史跡基肄城跡の散策環境改善、②第3回特別史跡基肄城跡ハイキング開催、③特別史跡基肄城跡ならびに基山(キザン)に関する企画展の3つです。
①では、散策環境や遺構環境を悪化させる草の除草や遊歩道の保全としての樹木伐採を4回行っております。


■史跡環境保全活動
②は令和7年3月20日、基肄城跡が特別史跡に指定された記念日に第3回特別史跡基肄城跡ハイキングを開催しております。3月下旬にしては異例な前日からの積雪にみまわれ雪山登山という珍しい景色の中を、町内外からお越しの58人のお客様を案内しました。




■第3回特別史跡基肄城跡ハイキング
③は事業②や後述する「基肄城を未来へつなぐ」シンポジウムと連携し、ディープな基肄城を伝える企画展を町立図書館郷土資料コーナーにて3月4日から23日まで開催いたしました。基山(キザン)に対する思いも展示し、基山町ご出身の漫画家 原泰久先生の直筆イラストと基肄城に対する思いをご寄稿いただき展示いたしました。


■基肄城を未来へつなぐ企画展
そして、一昨日、23日に「基肄城を未来へつなぐ」と題したシンポジウムが開催され、世界考古学会議会長であり九州大学大学院教授溝口孝司先生にお越しいただき「関連世界遺産から考える基肄城の未来」と題した基調講演、さらには久留米工業大学教授大森洋子先生にコーディネートしていただいた「基肄城を未来へつなぐ」シンポジウムが行われ、当会の福永副理事長も民間の立場から意見を述べるべく登壇し、基肄城の記念日にみんなが集い基肄城を舞台に様々な催し(創作劇、音楽祭、ディープな基肄城を知る濃い・来い・恋ハイキング、基肄城キャンプ、観月会、衣装を着ての歴史体験などなど)を行うような『基肄城まつり』を提案しております。また、きやま創作劇に出演し、現在、東映京都俳優部に所属してご活躍中の江島千智さんも登壇され、若い力でできることを考え情報発信などを実践していくことの大切さもご提案いただきました。


■溝口孝司先生による基調講演


■「基肄城を未来へつなぐ」パネルディスカッション
令和6年度の基山町からの受託事業、基山町主催事業と特別史跡基肄城跡に係る全ての取組が終了いたしました。


令和6年度はまもなく終わりますが、「基肄城を未来へつなぐ」ための一歩は昭和前期の久保山善映先生の活動から既に始まっています。そして今、基肄城・キザンを舞台に多くの方々が集い活動が再興しています。令和7年度には、何が始まるか、何が始められるのか、一つひとつ、一歩いっぽ進んでいきましょう。
みんなで・・・・
※2027年は基肄城跡史跡指定90周年、2037年は史跡指定100年です。
①では、散策環境や遺構環境を悪化させる草の除草や遊歩道の保全としての樹木伐採を4回行っております。


■史跡環境保全活動
②は令和7年3月20日、基肄城跡が特別史跡に指定された記念日に第3回特別史跡基肄城跡ハイキングを開催しております。3月下旬にしては異例な前日からの積雪にみまわれ雪山登山という珍しい景色の中を、町内外からお越しの58人のお客様を案内しました。




■第3回特別史跡基肄城跡ハイキング
③は事業②や後述する「基肄城を未来へつなぐ」シンポジウムと連携し、ディープな基肄城を伝える企画展を町立図書館郷土資料コーナーにて3月4日から23日まで開催いたしました。基山(キザン)に対する思いも展示し、基山町ご出身の漫画家 原泰久先生の直筆イラストと基肄城に対する思いをご寄稿いただき展示いたしました。


■基肄城を未来へつなぐ企画展
そして、一昨日、23日に「基肄城を未来へつなぐ」と題したシンポジウムが開催され、世界考古学会議会長であり九州大学大学院教授溝口孝司先生にお越しいただき「関連世界遺産から考える基肄城の未来」と題した基調講演、さらには久留米工業大学教授大森洋子先生にコーディネートしていただいた「基肄城を未来へつなぐ」シンポジウムが行われ、当会の福永副理事長も民間の立場から意見を述べるべく登壇し、基肄城の記念日にみんなが集い基肄城を舞台に様々な催し(創作劇、音楽祭、ディープな基肄城を知る濃い・来い・恋ハイキング、基肄城キャンプ、観月会、衣装を着ての歴史体験などなど)を行うような『基肄城まつり』を提案しております。また、きやま創作劇に出演し、現在、東映京都俳優部に所属してご活躍中の江島千智さんも登壇され、若い力でできることを考え情報発信などを実践していくことの大切さもご提案いただきました。
■溝口孝司先生による基調講演
■「基肄城を未来へつなぐ」パネルディスカッション
令和6年度の基山町からの受託事業、基山町主催事業と特別史跡基肄城跡に係る全ての取組が終了いたしました。


令和6年度はまもなく終わりますが、「基肄城を未来へつなぐ」ための一歩は昭和前期の久保山善映先生の活動から既に始まっています。そして今、基肄城・キザンを舞台に多くの方々が集い活動が再興しています。令和7年度には、何が始まるか、何が始められるのか、一つひとつ、一歩いっぽ進んでいきましょう。
みんなで・・・・
※2027年は基肄城跡史跡指定90周年、2037年は史跡指定100年です。
2025年03月09日
■基肄城顕彰建造物 往時の景観を取り戻す
令和6年度の基山町の事業で、基肄城顕彰建造物をはじめとした基山(キザン)の旧景観を少しでも取り戻す取組が、少しずつ、一歩いっぽ進められています。
基山(キザン)山頂は、かつて草原の山で、基肄城顕彰建造物の一つである天智天皇欽仰之碑(以下「欽仰之碑」)もタマタマ石の東側、小高い丘の上に独立して立っていました。ここ数年の状況は、欽仰之碑の横に樹木が繁茂し、夏場はこの木々の葉で右半分が隠れている状況でした。


【手入れ前の姿】
先週月曜日から、これらの樹木を地元の造園業者の方々が丁寧に伐採作業と後処理を行っていただき、金曜日に元あった姿を取り戻しています。


【手入れ後の姿 下は天智天皇欽仰之碑の背後から撮影】
 【昭和前期の姿】
【昭和前期の姿】
今年度から基山(キザン)の元あった姿を取り戻す取組が、この他に基山(キザン)を育てる有志の会「KIZANの会」が発足し、基山(キザン)の手入れ作業も始まっています。



【左:作業前 右:作業後】

【手入れ作業によって綺麗に整えられた中ノ尾礎石群】
※中ノ尾礎石群の手入れ作業の中で、太宰府天満宮の新年の行事「鷽替え神事」の際に使用される木うその素材となる「コシアブラ」の木が1本育っていました。この件については、日を改めて・・・・。
少しずつ、一歩いっぽ、かつての姿を取り戻していく基山(キザン)、基肄城を訪れ、どこが変わっていっているのか、頭の活性化「アハ」体験をしてみてはいかがでしょうか。
基山(キザン)山頂は、かつて草原の山で、基肄城顕彰建造物の一つである天智天皇欽仰之碑(以下「欽仰之碑」)もタマタマ石の東側、小高い丘の上に独立して立っていました。ここ数年の状況は、欽仰之碑の横に樹木が繁茂し、夏場はこの木々の葉で右半分が隠れている状況でした。


【手入れ前の姿】
先週月曜日から、これらの樹木を地元の造園業者の方々が丁寧に伐採作業と後処理を行っていただき、金曜日に元あった姿を取り戻しています。


【手入れ後の姿 下は天智天皇欽仰之碑の背後から撮影】
 【昭和前期の姿】
【昭和前期の姿】今年度から基山(キザン)の元あった姿を取り戻す取組が、この他に基山(キザン)を育てる有志の会「KIZANの会」が発足し、基山(キザン)の手入れ作業も始まっています。



【左:作業前 右:作業後】

【手入れ作業によって綺麗に整えられた中ノ尾礎石群】
※中ノ尾礎石群の手入れ作業の中で、太宰府天満宮の新年の行事「鷽替え神事」の際に使用される木うその素材となる「コシアブラ」の木が1本育っていました。この件については、日を改めて・・・・。
少しずつ、一歩いっぽ、かつての姿を取り戻していく基山(キザン)、基肄城を訪れ、どこが変わっていっているのか、頭の活性化「アハ」体験をしてみてはいかがでしょうか。
2025年03月02日
■『基肄城を未来へつなぐ』企画展 開催中
当会が基山町教育委員会からの受託事業の一つとして受けた「町内遺跡周知活用事業」の中の一つの柱である、『基肄城を未来へつなぐ』企画展が、当初予定の3月4日(火)開会を前倒しし、町教育委員会監理の元、昨日から基山町立図書館 郷土資料コーナーにて開会しています。

【基山町立図書館 郷土資料コーナーにて開催中】
基山町教育委員会が令和6年度に進めている「特別史跡基肄城跡活用推進事業」の3つの取組を深く知る展示として企画しました。
一つは、11月23日に開催された「基肄城跡の魅力発見バスツアー」、二つ目は3月20日に開催予定の「第3回特別史跡基肄城跡ハイキング」、そして特別史跡基肄城跡に関するシンポジウムとしては久しぶりの開催となる「特別史跡基肄城跡シンポジウム『基肄城を未来へつなぐ』」の3つの企画を深く知る展示を行っています。

基肄城の持つ『基本的価値』を知り、積み重ねられたきた人々の「思い」「想い」をはじめ、基山町御出身の漫画家 原先生の基肄城に対する「想い」も御寄せていただき展示しています。

そして、これまで平成24年以来、当会も含め官民協働で取り組んできた基肄城を素材とした様々な取組も紹介しています。
わが町の宝であり国の宝である「特別史跡基肄城跡」を未来へつなぐ取組は、一人ひとりの「思い」「想い」から、既に動き始まっています。
是非、企画展ご覧ください。

【基山町立図書館 郷土資料コーナーにて開催中】
基山町教育委員会が令和6年度に進めている「特別史跡基肄城跡活用推進事業」の3つの取組を深く知る展示として企画しました。
一つは、11月23日に開催された「基肄城跡の魅力発見バスツアー」、二つ目は3月20日に開催予定の「第3回特別史跡基肄城跡ハイキング」、そして特別史跡基肄城跡に関するシンポジウムとしては久しぶりの開催となる「特別史跡基肄城跡シンポジウム『基肄城を未来へつなぐ』」の3つの企画を深く知る展示を行っています。

基肄城の持つ『基本的価値』を知り、積み重ねられたきた人々の「思い」「想い」をはじめ、基山町御出身の漫画家 原先生の基肄城に対する「想い」も御寄せていただき展示しています。

そして、これまで平成24年以来、当会も含め官民協働で取り組んできた基肄城を素材とした様々な取組も紹介しています。
わが町の宝であり国の宝である「特別史跡基肄城跡」を未来へつなぐ取組は、一人ひとりの「思い」「想い」から、既に動き始まっています。
是非、企画展ご覧ください。
タグ :特別史跡基肄城跡
2025年02月11日
■令和6年度クロスロード文化講演会
基山・鳥栖・小郡の歴史文化を学習し、後世へ伝えていく取組を行っている「基山・鳥栖・小郡クロスロード文化研究会」の今年の文化講演会が、今日、鳥栖市立図書館2階視聴覚室で開催されました。
例年であれば、毎年11月開催されていますが、昨年の11月は様々なイベントが重なったこともあり、2月に開催ということになりました。
今回のテーマは、基山・鳥栖・小郡に共通する「どろどろ参り」が取り上げられ、関係する一町二市からそれぞれ報告がなされ、50名を超える方々にご参集いただいています。

●会長挨拶
基山町の報告は、当会の会員が行い、基山町史編さんや基山町歴史的風致維持向上計画策定にあたっての聞き取り調査や関係する文化遺産調査成果に基づく発表を行っています。

●基山町のどろどろ参りの報告
毎年、3月の第一土曜日に行っている「歴史散歩」のテーマの一つとして、この「どろどろ参り」の宗教色を帯びずに歴史資料としての仏様・札所巡りもいいのではないかと思ったところでした。
例年であれば、毎年11月開催されていますが、昨年の11月は様々なイベントが重なったこともあり、2月に開催ということになりました。
今回のテーマは、基山・鳥栖・小郡に共通する「どろどろ参り」が取り上げられ、関係する一町二市からそれぞれ報告がなされ、50名を超える方々にご参集いただいています。

●会長挨拶
基山町の報告は、当会の会員が行い、基山町史編さんや基山町歴史的風致維持向上計画策定にあたっての聞き取り調査や関係する文化遺産調査成果に基づく発表を行っています。

●基山町のどろどろ参りの報告
毎年、3月の第一土曜日に行っている「歴史散歩」のテーマの一つとして、この「どろどろ参り」の宗教色を帯びずに歴史資料としての仏様・札所巡りもいいのではないかと思ったところでした。
2024年12月07日
■令和6年度 第8回きやま創作劇公演
8回目を迎える「きやま創作劇」。
早いもので、8年目を迎えることとなりました。
これも、きやま創作劇を支えてくださっている多くの方々の御蔭と、心より深く深く感謝申し上げます。一歩いっぽ、一年いちねん、一回いっかいを大事に大切に歩んできた、その積み重ねです。

明日、第8回きやま創作劇 『永遠に君思う』公演の日です。
夏から歩んできたキャストだけでなく支えてくださった実に多くのご家族、スタッフ、関係者の皆さまのお力添えの御蔭で明日を迎えることができます。
今年は、きやま創作劇の原点たる「こころつないで」の歴史的背景に広がりと深みを持たせた作品になっています。是非、ご覧ください。

●今日の「通し稽古」の後の指導の様子

●基山町民会館小ホールでの歴代ポスター展示の様子
※毎年、きやま創作劇と連携し、「きやま創作劇を深く知る」展示を、基山町立図書館郷土資料コーナーにて行っています。併せて御覧ください。
早いもので、8年目を迎えることとなりました。
これも、きやま創作劇を支えてくださっている多くの方々の御蔭と、心より深く深く感謝申し上げます。一歩いっぽ、一年いちねん、一回いっかいを大事に大切に歩んできた、その積み重ねです。

明日、第8回きやま創作劇 『永遠に君思う』公演の日です。
夏から歩んできたキャストだけでなく支えてくださった実に多くのご家族、スタッフ、関係者の皆さまのお力添えの御蔭で明日を迎えることができます。
今年は、きやま創作劇の原点たる「こころつないで」の歴史的背景に広がりと深みを持たせた作品になっています。是非、ご覧ください。

●今日の「通し稽古」の後の指導の様子

●基山町民会館小ホールでの歴代ポスター展示の様子
※毎年、きやま創作劇と連携し、「きやま創作劇を深く知る」展示を、基山町立図書館郷土資料コーナーにて行っています。併せて御覧ください。
2024年11月30日
■基肄城月間
令和6年11月は、基山町(企画政策課、産業振興課)、基山町教育委員会(教育学習課)、きやま創作劇実行委員会、基肄かたろう会、(公財)古都大宰府保存協会、KBC九州朝日放送、エフエム佐賀、読売広告、そして当会とまさに官民協働の取組として『基肄城月間(基肄城ピクニックWEEKS)』が初めて展開されました。
基肄かたろう会による11月9日のツキイチ登山会にはじまり、11月24日のJRウォークまで毎週土日は「基肄城・キザン(基山)にひたる」、そんな11月でした。

【写真提供:基山町産業振興課・基山町教育委員会】
参加いただいた多くの皆さまからは、もっと基肄城のことが知りたい、キザン(基山)の自然が知りたいというお言葉や、来年3月に企画している「第3回基肄城跡ハイキング」への申し込み依頼、「つぎ」への期待までいただくなど、今回の取組の手ごたえを感じたひと月でした。
参加いただいた皆さま、協働いただいた各団体の皆さま、ありがとうございました。
基肄かたろう会による11月9日のツキイチ登山会にはじまり、11月24日のJRウォークまで毎週土日は「基肄城・キザン(基山)にひたる」、そんな11月でした。

【写真提供:基山町産業振興課・基山町教育委員会】
参加いただいた多くの皆さまからは、もっと基肄城のことが知りたい、キザン(基山)の自然が知りたいというお言葉や、来年3月に企画している「第3回基肄城跡ハイキング」への申し込み依頼、「つぎ」への期待までいただくなど、今回の取組の手ごたえを感じたひと月でした。
参加いただいた皆さま、協働いただいた各団体の皆さま、ありがとうございました。
2024年10月20日
■宝満神社の秋の大祭 園部くんち
10月20日(日)、本日、早朝午前7時から園部の鎮守・宝満神社の秋の大祭「園部くんち」が催行されています。
午前7時から、発御祭ならびに主祭神である玉依姫命様のお神輿への遷座祭が執り行われ、神社総代会長による辻御幣立と先導によって、御旅所までの御神幸が行われました。

■お下りの様子

■秋空の太陽の光に輝くお神輿
江戸時代(正徳6年(1716))に記された「基肄郡上郷神社記録」によれば、宝満神社は基肄城を築造した天智天皇の弟・天武天皇4年(676)の創建とされ、宝満山南麓にある竈門神社から勧請されたと伝えられています。
この園部くんちで執り行われる玉依姫命さまの御神幸は、江戸時代初期の慶安5年(1651)に神伽22人で行われたとされ、370年以上続けられています。
園部くんちの奉納芸能は大名行列で、お下り・お上りの道中を賑やかな雰囲気に創り上げます。

■大名行列の演舞
午後2時から、御旅所を出立するための発御祭が執り行われ、午後2時30分から150m先の宝満神社本宮までお上りが始まります。
宝満神社の園部くんち。
大人の方々による大名行列と合わせて、たくさんの子どもたちによる大名行列も珍しく、主祭神の玉依姫さまを先導していく様は、秋晴れの空のもと、多世代が交わる貴重な祭といえます。

子どもたちも参画しています。
午前7時から、発御祭ならびに主祭神である玉依姫命様のお神輿への遷座祭が執り行われ、神社総代会長による辻御幣立と先導によって、御旅所までの御神幸が行われました。

■お下りの様子

■秋空の太陽の光に輝くお神輿
江戸時代(正徳6年(1716))に記された「基肄郡上郷神社記録」によれば、宝満神社は基肄城を築造した天智天皇の弟・天武天皇4年(676)の創建とされ、宝満山南麓にある竈門神社から勧請されたと伝えられています。
この園部くんちで執り行われる玉依姫命さまの御神幸は、江戸時代初期の慶安5年(1651)に神伽22人で行われたとされ、370年以上続けられています。
園部くんちの奉納芸能は大名行列で、お下り・お上りの道中を賑やかな雰囲気に創り上げます。

■大名行列の演舞
午後2時から、御旅所を出立するための発御祭が執り行われ、午後2時30分から150m先の宝満神社本宮までお上りが始まります。
宝満神社の園部くんち。
大人の方々による大名行列と合わせて、たくさんの子どもたちによる大名行列も珍しく、主祭神の玉依姫さまを先導していく様は、秋晴れの空のもと、多世代が交わる貴重な祭といえます。

子どもたちも参画しています。
2024年08月17日
■「天神縁起画伝」限定公開
太宰府天満宮の御祭神である菅原道真公の生涯から太宰府天満宮の創建、霊験を描いた「天神縁起画伝」展が、今日と明日の二日間、基山町立図書館多目的室で限定公開されています。

明治時代の廃仏毀釈の折、天本茂左衛門氏によって太宰府の六度寺から招来されたとする画伝で、基山町古屋敷で大切に保管されていました。年に一度虫干しを兼ねて子どもたちへの読み聞かせが行われていたことにちなみ、年に一度、この時期に町立図書館多目的室を会場に展示が行われています。
天神縁起画伝、一般的には「天満宮縁起画伝」と呼称され、太宰府天満宮に現在も所蔵されているものをはじめ幾幅もの画伝がつくられ受け継がれてきています。基山町に招来された画伝は、かつての所在地の名称をとり「古屋敷本」と呼ばれています。
「古屋敷本」は、太宰府天満宮御所蔵の延寿王院本と絵画構成は同じで、太宰府へ来られた後の菅原道真公の描き方や建造物の部材の描き方に差異が見られますが、おおむね酷似しています。
かつては掛け軸として招来され、現在は、昭和31年に古屋敷の方々で御浄財を集め、屏風仕様に設えられています。その際、天満宮縁起画伝への理解が変容したのか、子どもたちへ語る物語の順番に再配列されたのかは定かではありませんが、順番が先の延寿王院本と異なる順番となっているのはご注意いただき御覧ください。
文道の神・菅原道真公ゆかりの絵画資料として、ご覧になっては如何でしょうか。


公開日:令和6年8月17日・18日
時間:午前10時から午後3時
場所:基山町立図書館 多目的室
※資料保存状態の確保ならびに施設利用の観点から、2日間の限定公開となっております。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

明治時代の廃仏毀釈の折、天本茂左衛門氏によって太宰府の六度寺から招来されたとする画伝で、基山町古屋敷で大切に保管されていました。年に一度虫干しを兼ねて子どもたちへの読み聞かせが行われていたことにちなみ、年に一度、この時期に町立図書館多目的室を会場に展示が行われています。
天神縁起画伝、一般的には「天満宮縁起画伝」と呼称され、太宰府天満宮に現在も所蔵されているものをはじめ幾幅もの画伝がつくられ受け継がれてきています。基山町に招来された画伝は、かつての所在地の名称をとり「古屋敷本」と呼ばれています。
「古屋敷本」は、太宰府天満宮御所蔵の延寿王院本と絵画構成は同じで、太宰府へ来られた後の菅原道真公の描き方や建造物の部材の描き方に差異が見られますが、おおむね酷似しています。
かつては掛け軸として招来され、現在は、昭和31年に古屋敷の方々で御浄財を集め、屏風仕様に設えられています。その際、天満宮縁起画伝への理解が変容したのか、子どもたちへ語る物語の順番に再配列されたのかは定かではありませんが、順番が先の延寿王院本と異なる順番となっているのはご注意いただき御覧ください。
文道の神・菅原道真公ゆかりの絵画資料として、ご覧になっては如何でしょうか。


公開日:令和6年8月17日・18日
時間:午前10時から午後3時
場所:基山町立図書館 多目的室
※資料保存状態の確保ならびに施設利用の観点から、2日間の限定公開となっております。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
2024年07月27日
令和6年度きやま創作劇『永遠(トワ)に君思う』始まり!
本日、午前10時から町民会館小ホールにて、令和6年度第8回きやま創作劇『永遠(トワ)に君思う』公演にむけた説明会が開催され、その後引き続き第1回練習へと移りました。

■松田一也基山町長からご挨拶いただきました。

■総指揮者 福永さんから、劇内容説明の様子
今回のテーマは、私たち「きやま」の思い(歴史)が詰まった山・基山(キザン)を舞台に、地主神(とこぬしのかみ)である荒穂大明神さまとキザン(基山)という神代の世界から、三韓統一を目指す新羅の策謀の渦にのみ込まれていった激動の7世紀、東アジア世界(新羅・百済・高句麗、そして倭)の国造り(国家形成)の物語です。
6月7日(金)に第1回きやま創作劇実行委員会が開催され、今年度も公演を行うこと、素材を基山町が今年度取り組む「基山(キザン)・基肄城さいこープロジェクト」と連携することが確認され、脚本づくりが大詰めをむかえます。


■7月22日開催の第2回きやま創作劇実行委員会
そして、7月20日(土)には、今日の説明会に先立ち、きのくに祭へ「きやま創作劇」宣伝隊が繰り出し、今年度の「永遠(トワ)に君思う」の宣伝を行っています。


■きやま創作劇宣伝隊(於 きのくに祭)
いよいよ今年も「きやま創作劇」の半年が始まります。
いつもの顔ぶれに、新たな仲間も加え『永遠(トワ)に君思う』公演にむけた一歩がスタートしました。
参画してくださる皆さま、くれぐれも、体調管理にはご留意くださり、12月8日(日)の公演のその日を、集った仲間みなでむかえましょう。
ご安全に・・・・・・!
追記
今年で、きやま創作劇が生まれて12年(前身の基山町立小中学校合同創作劇を含む)。キャストの中に唯一、平成24年(2012)12月公演から出演してくれている渡邉くんも20歳に。12年前の第1回公演の感想文(当時小学校2年生)に「今回のげきにさんかするのは、本当はいやでした。」とつづってくれています(基山の歴史と文化を語り継ぐ会、2013)。


基山の歴史と文化を語り継ぐ会(2013)『町史研究 きやま』創刊号

■松田一也基山町長からご挨拶いただきました。

■総指揮者 福永さんから、劇内容説明の様子
今回のテーマは、私たち「きやま」の思い(歴史)が詰まった山・基山(キザン)を舞台に、地主神(とこぬしのかみ)である荒穂大明神さまとキザン(基山)という神代の世界から、三韓統一を目指す新羅の策謀の渦にのみ込まれていった激動の7世紀、東アジア世界(新羅・百済・高句麗、そして倭)の国造り(国家形成)の物語です。
6月7日(金)に第1回きやま創作劇実行委員会が開催され、今年度も公演を行うこと、素材を基山町が今年度取り組む「基山(キザン)・基肄城さいこープロジェクト」と連携することが確認され、脚本づくりが大詰めをむかえます。


■7月22日開催の第2回きやま創作劇実行委員会
そして、7月20日(土)には、今日の説明会に先立ち、きのくに祭へ「きやま創作劇」宣伝隊が繰り出し、今年度の「永遠(トワ)に君思う」の宣伝を行っています。


■きやま創作劇宣伝隊(於 きのくに祭)
いよいよ今年も「きやま創作劇」の半年が始まります。
いつもの顔ぶれに、新たな仲間も加え『永遠(トワ)に君思う』公演にむけた一歩がスタートしました。
参画してくださる皆さま、くれぐれも、体調管理にはご留意くださり、12月8日(日)の公演のその日を、集った仲間みなでむかえましょう。
ご安全に・・・・・・!
追記
今年で、きやま創作劇が生まれて12年(前身の基山町立小中学校合同創作劇を含む)。キャストの中に唯一、平成24年(2012)12月公演から出演してくれている渡邉くんも20歳に。12年前の第1回公演の感想文(当時小学校2年生)に「今回のげきにさんかするのは、本当はいやでした。」とつづってくれています(基山の歴史と文化を語り継ぐ会、2013)。


基山の歴史と文化を語り継ぐ会(2013)『町史研究 きやま』創刊号
2024年06月01日
■令和6年度企画展『梁井家文書の世界』展開催中!
本日より基山町教育委員会主催の令和6年度企画展『梁井家文書の世界』展が開催されています。
当会が令和4年度・5年度に基山町教育委員会からの委託を受け実施した「梁井家文書」調査成果の一部の展示でもあり、当会がお手伝いした成果が多く展示されています。
今回は、「梁井家文書」の中の国境争論に焦点をあてた展示で、史跡として現在の「三国境」に遺る二国境石標や基山町-筑紫野市-小郡市のまさに三つの自治体の境界に建つ三国境石標とも併せて御覧いただければ、理解が深まると思います。


会期は、本日から7月28日(日)までとなっています。入館無料です。
開館時間:9:00~18:00(月曜休館)
是非、ご覧ください。
当会が令和4年度・5年度に基山町教育委員会からの委託を受け実施した「梁井家文書」調査成果の一部の展示でもあり、当会がお手伝いした成果が多く展示されています。
今回は、「梁井家文書」の中の国境争論に焦点をあてた展示で、史跡として現在の「三国境」に遺る二国境石標や基山町-筑紫野市-小郡市のまさに三つの自治体の境界に建つ三国境石標とも併せて御覧いただければ、理解が深まると思います。


会期は、本日から7月28日(日)までとなっています。入館無料です。
開館時間:9:00~18:00(月曜休館)
是非、ご覧ください。
2024年04月14日
■オキナグサ咲く「特別史跡基肄城跡」
現在、特別史跡基肄城跡がある基山(キザン)山頂には、希少植物である「オキナグサ」が咲いています。
昭和12年に国の史蹟に、昭和29年に同じく特別史跡に指定され、昭和前期からの自然環境と、地元の丸林、城戸の方々のご努力により、毎年防火帯として、森林の管理と野焼きが行われていました。さらには毎年暑いさなかに行っていただいている史跡地管理のための除草作業が行われてきたことから、雑草や樹木の繁茂からオキナグサは守られ、基山(キザン)の山頂に残されてきました。


■今年のオキナグサ
令和5年に環境省による「未来に残したい草原100選」に選ばれ、①特別史跡基肄城跡がある草原、②希少植物が群生する草原、そして③近代以来続けられている草スキーのある草原の3つの顔を持つ草原として選定されています。
3つの顔を持つ基山(キザン)です。
どれか一つを特化して守るのではなく、互いに共生できる、そんな取組を末永くお願いします。
古代の朝鮮式山城である 「特別史跡基肄城跡」の散策を目的に来られた際は、「特別史跡基肄(椽)城跡」指定石標周辺にオキナグサが花ひらいていますので、今しばらくの間、「お足元」に気を配りつつ特別史跡基肄城跡の散策をお楽しみください。

■特別史跡基肄(椽)城跡指定石標
※ご存知かと思いますが、「オキナグサ」の汁液に触れると皮膚炎を起こす可能性があります。ご注意ください。
※「オキナグサ」は、万葉集にも登場しますが、基肄城に関係深い万葉植物は「タチバナ」です。基山公園(草スキー場)多目的広場の入り口に植えられていますので併せて御覧ください。
昭和12年に国の史蹟に、昭和29年に同じく特別史跡に指定され、昭和前期からの自然環境と、地元の丸林、城戸の方々のご努力により、毎年防火帯として、森林の管理と野焼きが行われていました。さらには毎年暑いさなかに行っていただいている史跡地管理のための除草作業が行われてきたことから、雑草や樹木の繁茂からオキナグサは守られ、基山(キザン)の山頂に残されてきました。


■今年のオキナグサ
令和5年に環境省による「未来に残したい草原100選」に選ばれ、①特別史跡基肄城跡がある草原、②希少植物が群生する草原、そして③近代以来続けられている草スキーのある草原の3つの顔を持つ草原として選定されています。
3つの顔を持つ基山(キザン)です。
どれか一つを特化して守るのではなく、互いに共生できる、そんな取組を末永くお願いします。
古代の朝鮮式山城である 「特別史跡基肄城跡」の散策を目的に来られた際は、「特別史跡基肄(椽)城跡」指定石標周辺にオキナグサが花ひらいていますので、今しばらくの間、「お足元」に気を配りつつ特別史跡基肄城跡の散策をお楽しみください。

■特別史跡基肄(椽)城跡指定石標
※ご存知かと思いますが、「オキナグサ」の汁液に触れると皮膚炎を起こす可能性があります。ご注意ください。
※「オキナグサ」は、万葉集にも登場しますが、基肄城に関係深い万葉植物は「タチバナ」です。基山公園(草スキー場)多目的広場の入り口に植えられていますので併せて御覧ください。
2024年03月31日
■令和5年度事業(その2)
●関係事業
1.第7回きやま創作劇「この道は 基肄城が基肄城とならしむる時」公演
第7回を迎えるきやま創作劇は、今年度が特別史跡基肄城跡に関わる二つの記念の年であることから、基肄城跡顕彰建造物に焦点をあて、基肄城跡が国の第1類史蹟指定を受けるきっかけとなった先人たちの歩みを描きました。
2.第15回きやま展 展示支援
当会が始めた「きやま展」も、その後基山町教育委員会に引き継がれ、今年度で第15回を迎えました。第7回きやま創作劇「この道は」を深く知ることをテーマに展示支援を行いました。


左:第7回きやま創作劇 右:第15回きやま展
3.特別史跡基肄城跡整備基本設計のための現地調査
基山町教育委員会の「特別史跡基肄城跡整備基本設計」策定に先立ち、当会も含め特別史跡基肄城跡を舞台に活動している団体と現地踏査を行いました。道標サイン、解説サインの不足や、施設整備を行うのであればどのような内容(仕様)のものが求められるのか、など現地を歩きながら議論を重ねました。結果は、「特別史跡基肄城跡整備基本設計」としてまとめられています。
5.基山・鳥栖・小郡クロスロード文化研究会への参画
二市一町で構成される文化研究会へ、今年度も参画し、令和6年3月2日に開催された歴史散歩では安全管理を担っています。


左:現地調査時の議論の様子 右:歴史散歩
6.町行政への支援
基山町が事務局を担う各種委員会・審議会へ、会員諸氏が委員として参画し、基山町の歴史街づくり行政、文化財保護行政、そして教育委員会運営に指導・助言を行っています。
7.その他
史跡鞠智城跡ならびに山鹿の歴史的町並み整備地を研修する先進地視察の実施、会員諸氏の個人的な活動として、地域のお宮解説サインのリニューアル、特別史跡基肄城跡の手入れ活動、基山町が所蔵する諸資料の整理整頓なども行っています。


左:史跡鞠智城跡 右:山鹿市都市計画課の方よりの講話
令和5年度も、多くの会員の皆さまの協働、ご協力、できることを持ち寄る活動で、多様な取組を行うことができました。この場をお借りし、心より深く感謝申し上げます。
明日から、令和6年度が始まります。
どんな取組が、また出来事が待っているのでしょうか。
くれぐれも身体に気を付けて、楽しく、できることを持ち寄る活動を、一つひとつ大切に積み重ねていきたいと思います。
1.第7回きやま創作劇「この道は 基肄城が基肄城とならしむる時」公演
第7回を迎えるきやま創作劇は、今年度が特別史跡基肄城跡に関わる二つの記念の年であることから、基肄城跡顕彰建造物に焦点をあて、基肄城跡が国の第1類史蹟指定を受けるきっかけとなった先人たちの歩みを描きました。
2.第15回きやま展 展示支援
当会が始めた「きやま展」も、その後基山町教育委員会に引き継がれ、今年度で第15回を迎えました。第7回きやま創作劇「この道は」を深く知ることをテーマに展示支援を行いました。


左:第7回きやま創作劇 右:第15回きやま展
3.特別史跡基肄城跡整備基本設計のための現地調査
基山町教育委員会の「特別史跡基肄城跡整備基本設計」策定に先立ち、当会も含め特別史跡基肄城跡を舞台に活動している団体と現地踏査を行いました。道標サイン、解説サインの不足や、施設整備を行うのであればどのような内容(仕様)のものが求められるのか、など現地を歩きながら議論を重ねました。結果は、「特別史跡基肄城跡整備基本設計」としてまとめられています。
5.基山・鳥栖・小郡クロスロード文化研究会への参画
二市一町で構成される文化研究会へ、今年度も参画し、令和6年3月2日に開催された歴史散歩では安全管理を担っています。


左:現地調査時の議論の様子 右:歴史散歩
6.町行政への支援
基山町が事務局を担う各種委員会・審議会へ、会員諸氏が委員として参画し、基山町の歴史街づくり行政、文化財保護行政、そして教育委員会運営に指導・助言を行っています。
7.その他
史跡鞠智城跡ならびに山鹿の歴史的町並み整備地を研修する先進地視察の実施、会員諸氏の個人的な活動として、地域のお宮解説サインのリニューアル、特別史跡基肄城跡の手入れ活動、基山町が所蔵する諸資料の整理整頓なども行っています。


左:史跡鞠智城跡 右:山鹿市都市計画課の方よりの講話
令和5年度も、多くの会員の皆さまの協働、ご協力、できることを持ち寄る活動で、多様な取組を行うことができました。この場をお借りし、心より深く感謝申し上げます。
明日から、令和6年度が始まります。
どんな取組が、また出来事が待っているのでしょうか。
くれぐれも身体に気を付けて、楽しく、できることを持ち寄る活動を、一つひとつ大切に積み重ねていきたいと思います。
2024年03月31日
■令和5年度事業(その1)
今日、3月31日(日)をもって、令和5年度が幕をとじます。
今年度も、様々な事業を展開し、基山の歴史と文化を語り継ぐ活動を行ってまいりました。
●基山町教育委員会からの受託事業
1.町内遺跡周知活用事業(以下、「事業1」)
①特別史跡基肄城跡ハイキングの実施
令和5年11月23日(木) 第1回開催
令和6年3月20日(水) 第2回開催
この、特別史跡基肄城跡ハイキングでは、当会のほかに○きやま創作劇実行委員会、○基山の守り人、○基肄山歩会、○オキナグサ保存会、○基肄かたろう会など、基山(きざん)を舞台に活動している関係団体と連携し行いました。


左:第1回ハイキングの様子 右:第2回ハイキングの様子
また、基山町文化遺産ガイドボランティア養成講座と連携し、第2回特別史跡基肄城跡ハイキング開催にむけて特別史跡基肄城跡マップリニューアルを行い、当日資料として配布しています。


左:大礎石群の手入れ作業 右:基肄城内に仮設道標サインを設置(第1回ハイキング時)


基肄城内に仮設道標サインを設置(第2回ハイキング時 教育委員会と協働)
②企画展示
令和5年度が特別史跡基肄城跡に関わる二つの記念の年にあたることから、広く住民の皆さまにお伝えする展示を、基山町立図書館郷土資料コーナーにて行いました。
 企画展の様子
企画展の様子
2.文化遺産調査記録作成業務(以下、「事業2」)
①梁井家文書資料の翻刻、解読ならびに解説
令和4年度に基山町教育委員会から受託した、旧城戸村の庄屋文書である「梁井家文書」の中で、国境争論、荒穂神社関係文書の11点について、翻刻、解読並びに解説を行い、併せて住民の皆さまむけのリーフレットを作成しております。
その成果については、令和6年度に入り、基山町教育委員会ならびに御所有者と協議を行いつつ、基山町立図書館郷土資料コーナーにて展示などを通じてお伝えしていくことになろうかと思います。


【実績報告書 左:事業1、右事業2】
今年度も、様々な事業を展開し、基山の歴史と文化を語り継ぐ活動を行ってまいりました。
●基山町教育委員会からの受託事業
1.町内遺跡周知活用事業(以下、「事業1」)
①特別史跡基肄城跡ハイキングの実施
令和5年11月23日(木) 第1回開催
令和6年3月20日(水) 第2回開催
この、特別史跡基肄城跡ハイキングでは、当会のほかに○きやま創作劇実行委員会、○基山の守り人、○基肄山歩会、○オキナグサ保存会、○基肄かたろう会など、基山(きざん)を舞台に活動している関係団体と連携し行いました。


左:第1回ハイキングの様子 右:第2回ハイキングの様子
また、基山町文化遺産ガイドボランティア養成講座と連携し、第2回特別史跡基肄城跡ハイキング開催にむけて特別史跡基肄城跡マップリニューアルを行い、当日資料として配布しています。


左:大礎石群の手入れ作業 右:基肄城内に仮設道標サインを設置(第1回ハイキング時)


基肄城内に仮設道標サインを設置(第2回ハイキング時 教育委員会と協働)
②企画展示
令和5年度が特別史跡基肄城跡に関わる二つの記念の年にあたることから、広く住民の皆さまにお伝えする展示を、基山町立図書館郷土資料コーナーにて行いました。
 企画展の様子
企画展の様子2.文化遺産調査記録作成業務(以下、「事業2」)
①梁井家文書資料の翻刻、解読ならびに解説
令和4年度に基山町教育委員会から受託した、旧城戸村の庄屋文書である「梁井家文書」の中で、国境争論、荒穂神社関係文書の11点について、翻刻、解読並びに解説を行い、併せて住民の皆さまむけのリーフレットを作成しております。
その成果については、令和6年度に入り、基山町教育委員会ならびに御所有者と協議を行いつつ、基山町立図書館郷土資料コーナーにて展示などを通じてお伝えしていくことになろうかと思います。


【実績報告書 左:事業1、右事業2】
2024年03月10日
■荒穂神社石造鳥居の調査
昨日、3月9日午後1時より、秋の大祭・御神幸祭で知られる荒穂神社にて、江戸時代に寄進された石造鳥居の銘文調査を会員諸氏ならびに基肄かたろう会、文化遺産ガイドボランティアの総勢10名を超える皆さまで行いました。

■石造鳥居拓本採取の様子
調査にあたり、石造物ならびにお墓の研究で知られる大阪大谷大学教授の狭川真一先生をお迎えし、石造鳥居銘文の拓本の採り方や、午後5時からは、取得した拓本にある銘文からの読み解きについてのご指導、さらに中世から現代にかけてのお墓のあり方についての講話を行っていただいています。

■左が狭川真一先生
狭川先生の講話に、御遺体は「捨てる」ものという観念が当たり前だった中世の葬送観や、今の葬送儀礼の簡略化、意識の大きな変容など様々な視点からのお墓・墓地の見方についての講話に、聴講された皆さんも一様に驚きの声があがっていました。

■夕刻からの御講話の様子
ご指導いただいた狭川先生からも、笑顔で「こんなにたくさんの人たちと拓本を採るのは久しぶり。」という嬉しいお言葉をいただき、楽しいひと時となりました。
今回の銘文調査の成果は、作業風景ならびに拓本記録とともに基山町立図書館郷土資料コーナーにて展示させていただきます。お楽しみに。
 ■採取された鳥居銘文の拓本
■採取された鳥居銘文の拓本
奈良から大変お忙しい中、お越しいただいた狭川先生、ありがとうございました。
また、少々肌寒い午後でしたが、銘文調査に参画していただきました皆様、お疲れ様でした。そしてありがとうございました。
追記
昨日の午前中に特別史跡基肄城跡を訪れていただき、基肄かたろう会にてガイドし親交を深めた史跡首羅山遺跡で知られる久山町の「久山町歴史文化勉強会」の皆さまの飛び入り参加もあり、鳥居銘文調査の様子や基山(きざん)の守り神である荒穂神社を熱心に見学して帰られました。

■久山町の皆さまをお見送り
久山町の皆さま、ありがとうございました。
まだまだたくさんの文化遺産がわが町基山にはあります。
新たな発見・知識を蓄え展示や解説いたしますので、またのお越しをお待ちいたします。

■石造鳥居拓本採取の様子
調査にあたり、石造物ならびにお墓の研究で知られる大阪大谷大学教授の狭川真一先生をお迎えし、石造鳥居銘文の拓本の採り方や、午後5時からは、取得した拓本にある銘文からの読み解きについてのご指導、さらに中世から現代にかけてのお墓のあり方についての講話を行っていただいています。

■左が狭川真一先生
狭川先生の講話に、御遺体は「捨てる」ものという観念が当たり前だった中世の葬送観や、今の葬送儀礼の簡略化、意識の大きな変容など様々な視点からのお墓・墓地の見方についての講話に、聴講された皆さんも一様に驚きの声があがっていました。

■夕刻からの御講話の様子
ご指導いただいた狭川先生からも、笑顔で「こんなにたくさんの人たちと拓本を採るのは久しぶり。」という嬉しいお言葉をいただき、楽しいひと時となりました。
今回の銘文調査の成果は、作業風景ならびに拓本記録とともに基山町立図書館郷土資料コーナーにて展示させていただきます。お楽しみに。
 ■採取された鳥居銘文の拓本
■採取された鳥居銘文の拓本奈良から大変お忙しい中、お越しいただいた狭川先生、ありがとうございました。
また、少々肌寒い午後でしたが、銘文調査に参画していただきました皆様、お疲れ様でした。そしてありがとうございました。
追記
昨日の午前中に特別史跡基肄城跡を訪れていただき、基肄かたろう会にてガイドし親交を深めた史跡首羅山遺跡で知られる久山町の「久山町歴史文化勉強会」の皆さまの飛び入り参加もあり、鳥居銘文調査の様子や基山(きざん)の守り神である荒穂神社を熱心に見学して帰られました。

■久山町の皆さまをお見送り
久山町の皆さま、ありがとうございました。
まだまだたくさんの文化遺産がわが町基山にはあります。
新たな発見・知識を蓄え展示や解説いたしますので、またのお越しをお待ちいたします。
2023年12月19日
■「第15回きやま展」展示替え
昨日、令和5年12月17日に、第7回きやま創作劇『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』公演を終えたことを受け、覗きケースの展示替えを行いました。
劇に込められた様々な思いをパネル化するとともに、創作劇総指揮者である福永真理子氏が使っていた書き込みがある「台本」や作品の完成度を極限まで高めるための「ダメ出し」ノートを展示しています。

この「ダメ出し」は、12月10日の公演の直前、1回目公演を受け、2回目公演の完成度を高める上でも役立てられます。作品のブラッシュアップをやり続けることの大事さを見ることができる、貴重な資料です。
完成度を高める「求道」の精神は、様々な場面で必要とされることです。
しかし、一旦公演本番に入ると静観し、次の一歩への「反省(糧)」へとつなげていく。
創作劇では公演という舞台が、否が応でも到達点として理解しやすいですが、社会生活の中では、なかなか到達点が見えず、いつまでも「ブラッシュアップ」しつづけ、終わらない仕事ぶり、生活ぶりの方をお見かけすることが多くなりました。
結果、「成果」が出ず、「悩みのスパイラル」に埋没(沈没)していく。
そうならないためには、思い切った「区切り」を自ら課し、その区切りまではブラッシュアップを続け、その区切りで一旦終わらせ、その時に「反省」をつづり、次へ踏み出す一歩とすることが大切だと思います。
ひとの世に「完璧はない」
であるならば、「完璧」に近づける努力をする。
実は、「完璧」と思っている目標自体が、自分のちっぽけな小さな見識の中での疑似「完璧」であることに気づき、違った多様な見識を受け入れつつ「完璧」に近づけていくことが大事だと思います。
この時も「区切り」が節目として大事な役割を担います。

創作劇総指揮者の『福永ダメ出しノート』
そういう視点でもご覧ください。
劇に込められた様々な思いをパネル化するとともに、創作劇総指揮者である福永真理子氏が使っていた書き込みがある「台本」や作品の完成度を極限まで高めるための「ダメ出し」ノートを展示しています。

この「ダメ出し」は、12月10日の公演の直前、1回目公演を受け、2回目公演の完成度を高める上でも役立てられます。作品のブラッシュアップをやり続けることの大事さを見ることができる、貴重な資料です。
完成度を高める「求道」の精神は、様々な場面で必要とされることです。
しかし、一旦公演本番に入ると静観し、次の一歩への「反省(糧)」へとつなげていく。
創作劇では公演という舞台が、否が応でも到達点として理解しやすいですが、社会生活の中では、なかなか到達点が見えず、いつまでも「ブラッシュアップ」しつづけ、終わらない仕事ぶり、生活ぶりの方をお見かけすることが多くなりました。
結果、「成果」が出ず、「悩みのスパイラル」に埋没(沈没)していく。
そうならないためには、思い切った「区切り」を自ら課し、その区切りまではブラッシュアップを続け、その区切りで一旦終わらせ、その時に「反省」をつづり、次へ踏み出す一歩とすることが大切だと思います。
ひとの世に「完璧はない」
であるならば、「完璧」に近づける努力をする。
実は、「完璧」と思っている目標自体が、自分のちっぽけな小さな見識の中での疑似「完璧」であることに気づき、違った多様な見識を受け入れつつ「完璧」に近づけていくことが大事だと思います。
この時も「区切り」が節目として大事な役割を担います。

創作劇総指揮者の『福永ダメ出しノート』
そういう視点でもご覧ください。
2023年12月13日
感動と感謝
去る12月10日(日)、基山町民会館大ホールを舞台に、第7回きやま創作劇『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』の公演を迎えました。
着想から公演までの約半年間、長いようで短かった日々。
毎年、そう感じ公演の「この日」を迎えて今年で12年が過ぎています。
「到達点」の見えない第1回基山町立小中学校合同創作劇に、「勇気」を出して参画してくれた「子どもたち」も大きく成長し、青年として様々な場面に参画してくれていることは、一つひとつを積み重ねてきた者として感謝の念に堪えません。

■集ってくれたみなさん ありがとう!
我が町基山の年の瀬の風物詩ともなり、小中学校合同創作劇・きやま創作劇を巣立った多くの方々、また「きやま創作劇」を楽しみにしてくださっている観客の皆様が、公演のこの日に集ってくださっていることも、大きな喜びです。
未来の町民に伝えていきたいモノ、それが文化遺産です。文化遺産は「守らなければならない」モノ、「継続しなければならない」モノではなく、文化遺産を基点(素材)として今を生きる私たちが集うモノだと思います。
それを「きやま創作劇」が体現できていることは、文化遺産の持つ大きな力を示してくれていると思います。
今回の『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』は、基山に生き、六国史に記されるほどの「基肄城」のことを、この「村」の者は誰も知らない。このことを「嘆き」だけで終わらせず、我が身の実践を通して佐賀縣民を動かし、そして国の第一類史蹟へと押し上げた久保山善映先生の物語です。






■『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』
しかし、今回の劇には「きやま創作劇」総指揮者である福永真理子氏から「小中学校合同創作劇」「きやま創作劇」を経験し巣立っていったOG・OBたち、そして今、参画しているみなさんへ、久保山善映先生の「セリフ」に託して人生訓・メッセージが込められている。
自らの道を「極める」ことは、自らが切り拓くこと。
誰かが決めた道を漫然と歩くのとは違い、自らが決め、後悔しない人生を一歩一歩と歩みを進めること。
学歴社会が崩壊し、世の中では争いが起こり何が正義か分からなくなっている今。
人さまに迷惑をかけず、自らが決断し、学び、経験を積み重ね進むこと。
簡単なようで、「自ら決断する」ことから遠ざかっている世の中、何事も人さまに責任を転嫁する世の中(人)では理解し難く、とても難しいことかもしれません。
この世(現世)での出会い、共に「時」を同じくするのも一度きり
後悔のない人生を・・・・・・・。

着想から公演までの約半年間、長いようで短かった日々。
毎年、そう感じ公演の「この日」を迎えて今年で12年が過ぎています。
「到達点」の見えない第1回基山町立小中学校合同創作劇に、「勇気」を出して参画してくれた「子どもたち」も大きく成長し、青年として様々な場面に参画してくれていることは、一つひとつを積み重ねてきた者として感謝の念に堪えません。

■集ってくれたみなさん ありがとう!
我が町基山の年の瀬の風物詩ともなり、小中学校合同創作劇・きやま創作劇を巣立った多くの方々、また「きやま創作劇」を楽しみにしてくださっている観客の皆様が、公演のこの日に集ってくださっていることも、大きな喜びです。
未来の町民に伝えていきたいモノ、それが文化遺産です。文化遺産は「守らなければならない」モノ、「継続しなければならない」モノではなく、文化遺産を基点(素材)として今を生きる私たちが集うモノだと思います。
それを「きやま創作劇」が体現できていることは、文化遺産の持つ大きな力を示してくれていると思います。
今回の『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』は、基山に生き、六国史に記されるほどの「基肄城」のことを、この「村」の者は誰も知らない。このことを「嘆き」だけで終わらせず、我が身の実践を通して佐賀縣民を動かし、そして国の第一類史蹟へと押し上げた久保山善映先生の物語です。






■『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』
しかし、今回の劇には「きやま創作劇」総指揮者である福永真理子氏から「小中学校合同創作劇」「きやま創作劇」を経験し巣立っていったOG・OBたち、そして今、参画しているみなさんへ、久保山善映先生の「セリフ」に託して人生訓・メッセージが込められている。
自らの道を「極める」ことは、自らが切り拓くこと。
誰かが決めた道を漫然と歩くのとは違い、自らが決め、後悔しない人生を一歩一歩と歩みを進めること。
学歴社会が崩壊し、世の中では争いが起こり何が正義か分からなくなっている今。
人さまに迷惑をかけず、自らが決断し、学び、経験を積み重ね進むこと。
簡単なようで、「自ら決断する」ことから遠ざかっている世の中、何事も人さまに責任を転嫁する世の中(人)では理解し難く、とても難しいことかもしれません。
この世(現世)での出会い、共に「時」を同じくするのも一度きり
後悔のない人生を・・・・・・・。

2023年12月08日
■第7回きやま創作劇『この道は』公演迫る!
いよいよ公演のその日まで2日前となりました。
キャスト・スタッフの皆さん、いままで培ってきた自分を信じて、公演の日を迎えましょう。
あとは久保山善映先生、梁井幾太郎村長、そして基山のたくさんのご先祖様たちが見守ってくださいます。
 ■片隅でたたずむ小道具たち
■片隅でたたずむ小道具たち
『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』
皆が持てる力を持ち寄り、精一杯演じます。
ご期待ください!

キャスト・スタッフの皆さん、いままで培ってきた自分を信じて、公演の日を迎えましょう。
あとは久保山善映先生、梁井幾太郎村長、そして基山のたくさんのご先祖様たちが見守ってくださいます。
 ■片隅でたたずむ小道具たち
■片隅でたたずむ小道具たち『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』
皆が持てる力を持ち寄り、精一杯演じます。
ご期待ください!

2023年11月24日
■第1回特別史跡基肄城跡ハイキング開催
基肄城跡を巡るイベント開催のご要望が多く寄せられていた中、基山町教育委員会主催で久しぶりに特別史跡基肄城跡を巡るイベントが、令和5年11月23日(木)に開催されました。
当会がイベント運営を受託したこともあり、特別史跡基肄城跡がある基山(きざん)に関わる民間団体と協働、連携し、多くの町民が関わる取組としました。


【上:受付の様子 下:登山開始】
最終的に55名のお客様を迎え、「特別史跡基肄城跡ハイキング」がスタートし、山頂では基肄城跡顕彰建造物の一つ、天智天皇欽仰之碑建立90年を記念するイベントとして、第7回きやま創作劇『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』のキャストによるダイジェスト公演が行われ、その後、私たちの思いを基山の先人達に届けようと、シャボン玉にのせて飛ばしました。

【きやま創作劇キャストによるダイジェスト公演】

【シャボン玉に思いを乗せて】
また、90年前の天智天皇欽仰之碑除幕式での写真を思い起させる、参集した皆さまとの記念写真撮影は、感慨深いものでした。この時撮影した写真は、12月5日から基山町立図書館郷土資料コーナーにて開催される第15回『きやま展』にて展示予定です。参集された皆さま、ありがとうございました。
その後、6班に分かれ基肄城跡を基肄かたろう会の解説によってハイキングしていただき、予定の時間をややオーバーしましたが、アンケート結果からは多くの方々に満足いただく取組となりました。



一方、今回の取組では、様々な出来事にも遭遇したにも関わらず、基肄城跡の解説を運営していただいた基肄かたろう会ならびに基肄山歩会の皆さまの臨機対応能力の高さに救われ、大きな事故もなく終わることができました。ありがとうございました。
結びに、今回の取組に参画していただいたお客様、基肄かたろう会、基肄山歩会、基山の守り人、そして、きやま創作劇実行委員会の皆さまに、心より深く感謝申し上げます。
来年の3月20日には、基肄城跡が特別史跡に格上げ指定されて70年を迎えます。
この日にも、第2回基肄城跡ハイキングを今回の反省を踏まえ、また違った濃い取組として開催いたします。ご参加お待ちいたします。
当会がイベント運営を受託したこともあり、特別史跡基肄城跡がある基山(きざん)に関わる民間団体と協働、連携し、多くの町民が関わる取組としました。


【上:受付の様子 下:登山開始】
最終的に55名のお客様を迎え、「特別史跡基肄城跡ハイキング」がスタートし、山頂では基肄城跡顕彰建造物の一つ、天智天皇欽仰之碑建立90年を記念するイベントとして、第7回きやま創作劇『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』のキャストによるダイジェスト公演が行われ、その後、私たちの思いを基山の先人達に届けようと、シャボン玉にのせて飛ばしました。

【きやま創作劇キャストによるダイジェスト公演】

【シャボン玉に思いを乗せて】
また、90年前の天智天皇欽仰之碑除幕式での写真を思い起させる、参集した皆さまとの記念写真撮影は、感慨深いものでした。この時撮影した写真は、12月5日から基山町立図書館郷土資料コーナーにて開催される第15回『きやま展』にて展示予定です。参集された皆さま、ありがとうございました。
その後、6班に分かれ基肄城跡を基肄かたろう会の解説によってハイキングしていただき、予定の時間をややオーバーしましたが、アンケート結果からは多くの方々に満足いただく取組となりました。



一方、今回の取組では、様々な出来事にも遭遇したにも関わらず、基肄城跡の解説を運営していただいた基肄かたろう会ならびに基肄山歩会の皆さまの臨機対応能力の高さに救われ、大きな事故もなく終わることができました。ありがとうございました。
結びに、今回の取組に参画していただいたお客様、基肄かたろう会、基肄山歩会、基山の守り人、そして、きやま創作劇実行委員会の皆さまに、心より深く感謝申し上げます。
来年の3月20日には、基肄城跡が特別史跡に格上げ指定されて70年を迎えます。
この日にも、第2回基肄城跡ハイキングを今回の反省を踏まえ、また違った濃い取組として開催いたします。ご参加お待ちいたします。
2023年10月14日
■特別史跡基肄城跡ハイキング!
私たちの町の宝、特別史跡基肄城跡は、東アジア世界に広がる壮大な歴史を物語る遺産として日本遺産「西の都」として認定を受けています。
史跡内には基肄城に関わる様々な文化財のみならず基山の先人達の想いが詰まった基肄城を顕彰する建造物、そしてタマタマ石や謎のくぼ地など、どこにもない、ここだけにしかない文化遺産が数多く点在しています。

【大礎石群(大礎石建物)】
これら様々な文化財・文化遺産の解説を聞きながらハイキングしてみませんか?
そして「過去の基肄城」を知り、これからの「未来の基肄城」をイメージしながら、気軽に楽しく散策してみませんか?

【主催:基山町教育委員会】
※当会が企画・運営を受託し、町民で構成される様々な団体と協働で取り組んでいます。
特別史跡基肄城跡は、去る今年の6月10日は、基山(きざん)山頂にある天智天皇欽仰之碑や通天洞などが建設されて90年の月日が経過し、来年の3月20日で佐賀県初の特別史跡に指定されて70周年を迎えます。
この二つの「記念の日」と、そこに込められた90年前、70年前の基山に生きた方々の想いを共有し、基肄城に秘められた「ヒミツ」に触れながら歩きます。

11月23日の当日、山頂では「きやま創作劇実行委員会」や「基肄かたろう会」と連携した記念イベントも企画しています。
この「基肄城跡ハイキング」は、上記二つの団体の他に基山(きざん)にこれまで深く関わってこられた様々な団体の皆さまと協働で行っています。
お楽しみに!
※明治22年の4ヶ村合併によって誕生した「基山村」の名称と山の名称「基山」が重複することから、基山町民の皆さんは町の名前は「きやま」、山の名前は「きざん」と呼び分けています。
史跡内には基肄城に関わる様々な文化財のみならず基山の先人達の想いが詰まった基肄城を顕彰する建造物、そしてタマタマ石や謎のくぼ地など、どこにもない、ここだけにしかない文化遺産が数多く点在しています。

【大礎石群(大礎石建物)】
これら様々な文化財・文化遺産の解説を聞きながらハイキングしてみませんか?
そして「過去の基肄城」を知り、これからの「未来の基肄城」をイメージしながら、気軽に楽しく散策してみませんか?

【主催:基山町教育委員会】
※当会が企画・運営を受託し、町民で構成される様々な団体と協働で取り組んでいます。
特別史跡基肄城跡は、去る今年の6月10日は、基山(きざん)山頂にある天智天皇欽仰之碑や通天洞などが建設されて90年の月日が経過し、来年の3月20日で佐賀県初の特別史跡に指定されて70周年を迎えます。
この二つの「記念の日」と、そこに込められた90年前、70年前の基山に生きた方々の想いを共有し、基肄城に秘められた「ヒミツ」に触れながら歩きます。

11月23日の当日、山頂では「きやま創作劇実行委員会」や「基肄かたろう会」と連携した記念イベントも企画しています。
この「基肄城跡ハイキング」は、上記二つの団体の他に基山(きざん)にこれまで深く関わってこられた様々な団体の皆さまと協働で行っています。
お楽しみに!
※明治22年の4ヶ村合併によって誕生した「基山村」の名称と山の名称「基山」が重複することから、基山町民の皆さんは町の名前は「きやま」、山の名前は「きざん」と呼び分けています。