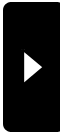2018年04月18日
■第3回きやま創作劇 はじまり、はじまり~っ!!
昨日、第3回きやま創作劇公演にむけて実施団体が会し、第1回きやま創作劇実行委員会実務者会議が開催されました。
当会も参画している「きやま創作劇実行委員会」メンバー、町役場からは、事業主管課であるまちづくり課、子どもたちに関係する教育学習課の方々が参集し、新年度を迎え新しいメンバーも加え、①昨年度の反省の確認、②今年度へむけての改善や方法、③公演日までのスケジュール等について意見が交わされました。
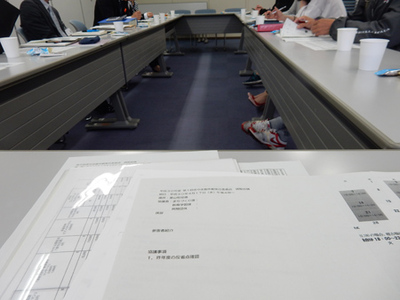
公演日は、昨年末の反省会の折に諸事議論されましたが、例年どおり、12月のふれあいフェスタの日である、平成30年12月9日(日)となり、それにむけた参画者むけ説明会、第1回練習の日などが決められていきました。

■話し合いの様子
さあ、今年のテーマは、何でしょうか?
「創造の泉」から漏れ出てくる情報から想像すると、江戸時代末期(幕末)から明治時代の基山を素材とした劇で、激動の時代を生き、我が町基山の発展に力を尽くされた多くの方々が登場するようです・・・・。政治・経済はもとより文化面や生活に至るまで、近代のきやまを描く物語が皆さんの前に繰り広げられるのではないかと・・・思います。
今年の創作劇の全貌は・・・6月中旬開催予定の劇説明会の時に
・・・・・・お楽しみに!
※きやま創作劇に関するブログを、近日中に基山WEBの駅(基山町公式HP内)に開設します。公演に関する情報はもとより、練習日や練習会場など創作劇制作に関わる諸情報を掲示していきますので、創作劇に関わる皆さんは、見逃さないように、ご注意!
当会も参画している「きやま創作劇実行委員会」メンバー、町役場からは、事業主管課であるまちづくり課、子どもたちに関係する教育学習課の方々が参集し、新年度を迎え新しいメンバーも加え、①昨年度の反省の確認、②今年度へむけての改善や方法、③公演日までのスケジュール等について意見が交わされました。
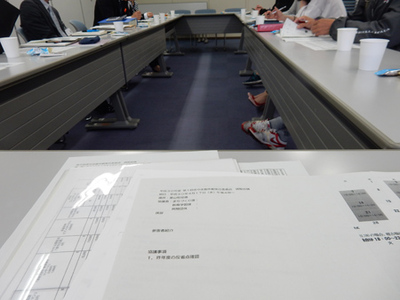
公演日は、昨年末の反省会の折に諸事議論されましたが、例年どおり、12月のふれあいフェスタの日である、平成30年12月9日(日)となり、それにむけた参画者むけ説明会、第1回練習の日などが決められていきました。

■話し合いの様子
さあ、今年のテーマは、何でしょうか?
「創造の泉」から漏れ出てくる情報から想像すると、江戸時代末期(幕末)から明治時代の基山を素材とした劇で、激動の時代を生き、我が町基山の発展に力を尽くされた多くの方々が登場するようです・・・・。政治・経済はもとより文化面や生活に至るまで、近代のきやまを描く物語が皆さんの前に繰り広げられるのではないかと・・・思います。
今年の創作劇の全貌は・・・6月中旬開催予定の劇説明会の時に
・・・・・・お楽しみに!
※きやま創作劇に関するブログを、近日中に基山WEBの駅(基山町公式HP内)に開設します。公演に関する情報はもとより、練習日や練習会場など創作劇制作に関わる諸情報を掲示していきますので、創作劇に関わる皆さんは、見逃さないように、ご注意!
2018年03月04日
■平成29年度 歴史散歩開催
昨日、3日(土)に基山・鳥栖・小郡クロスーロード文化研究会主催の歴史散歩が開催されました。
この歴史散歩も3月第一土曜日開催と定例化し、リピーターの方々も多く詰め掛け100名を超える方々に参集いただき、今年も盛会に終わりました。

■開催前スタッフミーティング時の会長挨拶の様子
今年は、「荘園を歩く」と題し、小倉庄、奈良田庄と基山から鳥栖を舞台に歩きました。
幸い、暑くもなく寒くもなく、ちょうどよい気候のもと、歩いていただけたと「天」の神さまに感謝しました。

■北奈良田八幡神社での解説の様子
まだまだ、ガイドを担当した私たちには、知りたいこと、学びたいことがたくさんあります。新たな話を聞きに、またの機会に再び御出で下さい。
参集いただきました皆様、ありがとうございました。
また、スタッフの皆さま、お疲れさまでした。

終着場所のJR田代駅にて、閉会挨拶の様子
この歴史散歩も3月第一土曜日開催と定例化し、リピーターの方々も多く詰め掛け100名を超える方々に参集いただき、今年も盛会に終わりました。

■開催前スタッフミーティング時の会長挨拶の様子
今年は、「荘園を歩く」と題し、小倉庄、奈良田庄と基山から鳥栖を舞台に歩きました。
幸い、暑くもなく寒くもなく、ちょうどよい気候のもと、歩いていただけたと「天」の神さまに感謝しました。

■北奈良田八幡神社での解説の様子
まだまだ、ガイドを担当した私たちには、知りたいこと、学びたいことがたくさんあります。新たな話を聞きに、またの機会に再び御出で下さい。
参集いただきました皆様、ありがとうございました。
また、スタッフの皆さま、お疲れさまでした。

終着場所のJR田代駅にて、閉会挨拶の様子
2017年12月11日
■第2回創作劇『八ツ並の姫』終演
公演の熱気が冷めやらぬ町民会館大ホールから一夜あけ、劇中のもう一つの「主役たち」である道具類の運び出しが行われました。
秋から有志の皆さんによってつくり上げられてきた道具たちも、「ホッ」とした様子で舞台にたたずんでいました。

疲れを癒す間もなく、大ホール舞台から次々に運び出され、次の出番まで倉庫の中で半年の眠りにつきます。

道具たち、「お疲れ様でした!」
秋から有志の皆さんによってつくり上げられてきた道具たちも、「ホッ」とした様子で舞台にたたずんでいました。

疲れを癒す間もなく、大ホール舞台から次々に運び出され、次の出番まで倉庫の中で半年の眠りにつきます。

道具たち、「お疲れ様でした!」
2017年12月11日
■皆さまの成長を感じて
第2回きやま創作劇『八ツ並の姫 観音様になったお姫様』公演、多くの皆さまにご来場いただきましたこと、心より深く感謝申し上げます。
今年の夏から半年間、日々練習を重ね、昨日の本番を迎えることができました。
これも、最後の挨拶で当会々長がご挨拶申し上げましたが、支えてくださった多くの関係者の皆さまのお陰と心より感謝申し上げます。
また、お忙しい中駆けつけてくださった、『八ツ並の姫』の物語にゆかり深い太田山安生寺の庵主様、ありがとうございました。

●結びの挨拶の様子
一年前の感動の場面に立ち合い、そして再び新しいメンバーを加え皆が集い、記念撮影の場に立ち会うことができた幸せをいただいたことに感謝いたしております。
創作劇に関わっていただき、支えてくださった多くの皆さま、心より深く深く感謝申し上げます。有難うございました。
また、集うことができることを祈り、その日まで・・・・・
総指揮を執っていただいた福永真理子さん、お疲れさまでした。

今年の夏から半年間、日々練習を重ね、昨日の本番を迎えることができました。
これも、最後の挨拶で当会々長がご挨拶申し上げましたが、支えてくださった多くの関係者の皆さまのお陰と心より感謝申し上げます。
また、お忙しい中駆けつけてくださった、『八ツ並の姫』の物語にゆかり深い太田山安生寺の庵主様、ありがとうございました。

●結びの挨拶の様子
一年前の感動の場面に立ち合い、そして再び新しいメンバーを加え皆が集い、記念撮影の場に立ち会うことができた幸せをいただいたことに感謝いたしております。
創作劇に関わっていただき、支えてくださった多くの皆さま、心より深く深く感謝申し上げます。有難うございました。
また、集うことができることを祈り、その日まで・・・・・
総指揮を執っていただいた福永真理子さん、お疲れさまでした。

2017年12月09日
■第2回きやま創作劇『八ツ並の姫』開演!
明日、第2回きやま創作劇『八ツ並の姫 観音様になったお姫様』開演です。
夏から始まった厳しい練習を乗り越え、今、参集した仲間が持てる力の全てを出し切り演じます。どうか、あの感動を再び・・・・・。
【公演時間】 公演時間:1時間30分を予定しています。
①午前11時開場 午前11時30分開演
②午後3時開場 午後3時30分開演

●紙芝居『八ツ並の姫 観音様になったお姫様』より
【公演場所】
基山町民会館 大ホール(基山町役場横)・・・JR基山駅から徒歩20分
※ふれあいフェスタが同時開催中です。駐車場は、誘導員の指示に従ってください。
なお、所定の駐車場が遠い場合があります。早めにご来場ください。
【入場料】無料
夏から始まった厳しい練習を乗り越え、今、参集した仲間が持てる力の全てを出し切り演じます。どうか、あの感動を再び・・・・・。
【公演時間】 公演時間:1時間30分を予定しています。
①午前11時開場 午前11時30分開演
②午後3時開場 午後3時30分開演

●紙芝居『八ツ並の姫 観音様になったお姫様』より
【公演場所】
基山町民会館 大ホール(基山町役場横)・・・JR基山駅から徒歩20分
※ふれあいフェスタが同時開催中です。駐車場は、誘導員の指示に従ってください。
なお、所定の駐車場が遠い場合があります。早めにご来場ください。
【入場料】無料
2017年12月08日
■公演 迫る!
第2回きやま創作劇『八ツ並の姫』公演まで、あと2日となりました。
役者の皆さん、スタッフの皆さん、これまで培ってきた思いを全て出し切ってください。
劇中で使用される様々な大道具、小道具、衣装は、すべてスタッフの皆さんが夏からつくり上げてこられました。毎年のことですが、知識と技の結晶とでもいえるモノに仕上がり、まさに一つ一つの作品といえる域まで達しています。
創作劇に結集する知恵、力、技、どれが欠けても舞台を彩ることはできません。すべてが結集した姿を10日の公演で御覧ください。
さあ、観世音菩薩様を味方につけるために、「持てる私たちの力を、すべて出し尽くさせてください。観世音菩薩様!」と心に抱き、あの瞬間を目指して・・・。
■創作劇観劇への豆知識 その3
劇中には、様々な道具類がスタッフの手によってつくり上げられています。
劇のクライマックスで登場する古井戸。

八ツ並の姫があやまって落ちてしまう、この古井戸もスタッフの苦労のすえつくり上げられました。井戸の「井」の字を表現するように板材を横方向に組み合わせた井戸で、上から見ると四角形をしています。井戸には木材を組み合わせたもの、石を積んでつくられたものがありますが、八ツ並の姫の舞台となる平安時代の多くは、板材を組み合わせてつくられたものが一般的でした。

■大宰府条坊跡でみつかった井戸(調査報告書より)

■大宰府条坊跡でみつかった井戸の模式図
やや時代は下り、14世紀の室町時代の絵図に、当時の井戸の様子が描かれています。

■不動利益縁起(14世紀 東京国立博物館蔵)
役者の皆さん、スタッフの皆さん、これまで培ってきた思いを全て出し切ってください。
劇中で使用される様々な大道具、小道具、衣装は、すべてスタッフの皆さんが夏からつくり上げてこられました。毎年のことですが、知識と技の結晶とでもいえるモノに仕上がり、まさに一つ一つの作品といえる域まで達しています。
創作劇に結集する知恵、力、技、どれが欠けても舞台を彩ることはできません。すべてが結集した姿を10日の公演で御覧ください。
さあ、観世音菩薩様を味方につけるために、「持てる私たちの力を、すべて出し尽くさせてください。観世音菩薩様!」と心に抱き、あの瞬間を目指して・・・。
■創作劇観劇への豆知識 その3
劇中には、様々な道具類がスタッフの手によってつくり上げられています。
劇のクライマックスで登場する古井戸。

八ツ並の姫があやまって落ちてしまう、この古井戸もスタッフの苦労のすえつくり上げられました。井戸の「井」の字を表現するように板材を横方向に組み合わせた井戸で、上から見ると四角形をしています。井戸には木材を組み合わせたもの、石を積んでつくられたものがありますが、八ツ並の姫の舞台となる平安時代の多くは、板材を組み合わせてつくられたものが一般的でした。

■大宰府条坊跡でみつかった井戸(調査報告書より)

■大宰府条坊跡でみつかった井戸の模式図
やや時代は下り、14世紀の室町時代の絵図に、当時の井戸の様子が描かれています。

■不動利益縁起(14世紀 東京国立博物館蔵)
2017年12月07日
日常に光をあてるひと 舟木千早
第2回きやま創作劇『八ツ並の姫』の素材となる「観音さまになったお姫様」を私たちに伝えてくださった方が、舟木千早氏、その人です。
舟木千早氏は、明治42年に基山村長野(現7区)で生まれ、昭和16年に逝去されるまで、私たちの感性では当たり前のことに光をあて、芸術の域まで昇華させ、今を生きる私たちに気づきを与えてくださった方です。
第1回きやま創作劇「ホタル列車」で子どもたちが口ずさんだ、「ホタルの提灯」
ホタルがさ かはべでさ ちいさな ちょうちん とぼすとさ
ホタルがさ くさはでさ なんだかさ おとしもの さがすとさ
ハッパがさ みんなでさ いじわる おとしもの かくすとさ
これも舟木千早氏の詩です。
芸術活動は、特別なことではなく、日常に目をむけ光輝く様を見る力、それを見る(知る)意識から生まれてくるということを私たちに伝えてくださっています。
今を生きる私たちは、特別なことを特別な人が決めるという錯覚に囚われています。自らの感性で感じ、そして表現する時代へ移ってきています。そのことに敏感に反応し適応することが求められているのではないかと思います。時にネット社会を見るにつけて。
舟木千早氏の作品は、まさに今を生きる私たちへの提言と受け止めたとき、師と呼べる方のお一人と言えます。
■創作劇観劇への豆知識 その2
劇中で舟木千早役の女の子が着ている衣装は、舟木千早先生がかつて着ておられたお着物です。偶然にも、衣装の寸法合わせをすることもなく、ピッタリそのまま着こなしてくれています。落ち着いたセリフの云いまわし、お写真から私たちが想像する舟木先生がそのまま現出してくださっているかのような錯覚にとらわれます。

■子どもたちに「八ツ並の姫」を語る千早氏(八ツ並の姫の一場面)
舟木千早氏は、明治42年に基山村長野(現7区)で生まれ、昭和16年に逝去されるまで、私たちの感性では当たり前のことに光をあて、芸術の域まで昇華させ、今を生きる私たちに気づきを与えてくださった方です。
第1回きやま創作劇「ホタル列車」で子どもたちが口ずさんだ、「ホタルの提灯」
ホタルがさ かはべでさ ちいさな ちょうちん とぼすとさ
ホタルがさ くさはでさ なんだかさ おとしもの さがすとさ
ハッパがさ みんなでさ いじわる おとしもの かくすとさ
これも舟木千早氏の詩です。
芸術活動は、特別なことではなく、日常に目をむけ光輝く様を見る力、それを見る(知る)意識から生まれてくるということを私たちに伝えてくださっています。
今を生きる私たちは、特別なことを特別な人が決めるという錯覚に囚われています。自らの感性で感じ、そして表現する時代へ移ってきています。そのことに敏感に反応し適応することが求められているのではないかと思います。時にネット社会を見るにつけて。
舟木千早氏の作品は、まさに今を生きる私たちへの提言と受け止めたとき、師と呼べる方のお一人と言えます。
■創作劇観劇への豆知識 その2
劇中で舟木千早役の女の子が着ている衣装は、舟木千早先生がかつて着ておられたお着物です。偶然にも、衣装の寸法合わせをすることもなく、ピッタリそのまま着こなしてくれています。落ち着いたセリフの云いまわし、お写真から私たちが想像する舟木先生がそのまま現出してくださっているかのような錯覚にとらわれます。

■子どもたちに「八ツ並の姫」を語る千早氏(八ツ並の姫の一場面)
2017年12月03日
第2回きやま創作劇『八ツ並の姫』総練習
本日、午後から第2回きやま創作劇『八ツ並の姫』公演にむけた総練習が、基山町民会館大ホールで行われました。
大道具・小道具、役者さんたちへの衣装着せ・化粧が行われ、音響、映像も入り本番さながらの流れの舞台確認が行われています。総指揮者・福永さんの諸注意も飛ぶ中で、皆が一丸となって公演へむけて取り組む姿は真剣そのものでした。

●劇中の一場面
あと一週間、ゴールを目指すのではなく、さらなる高みを目指す気持ちで突き進んでください。きっと、その先には感動の物語が待ってます。

●姫の輿入れの様子
■創作劇観劇への豆知識 その1
松田一也町長も役者の一人として登場します。
どこに出られているのかは秘密です。探してみてくださいね!
大道具・小道具、役者さんたちへの衣装着せ・化粧が行われ、音響、映像も入り本番さながらの流れの舞台確認が行われています。総指揮者・福永さんの諸注意も飛ぶ中で、皆が一丸となって公演へむけて取り組む姿は真剣そのものでした。

●劇中の一場面
あと一週間、ゴールを目指すのではなく、さらなる高みを目指す気持ちで突き進んでください。きっと、その先には感動の物語が待ってます。

●姫の輿入れの様子
■創作劇観劇への豆知識 その1
松田一也町長も役者の一人として登場します。
どこに出られているのかは秘密です。探してみてくださいね!
2017年12月03日
舞台設定始まる!
第2回きやま創作劇「八ツ並の姫」の公演まで、1週間。
昨日、2日午後には本番へむけた舞台設定が行われました。八ツ並長者屋敷セットが姿を現し、いよいよ本番間近という雰囲気が舞台を包み始めています。

■舞台セット設営

■姫の嫁入り道具を運ぶ荷車飾りにアイロンがけする福永さん
さあ、あと少し、今日は全体通しの「総練習」です。
今まで培ってきた「自分」を信じて演じきってください。役者も、スタッフも。
昨日、2日午後には本番へむけた舞台設定が行われました。八ツ並長者屋敷セットが姿を現し、いよいよ本番間近という雰囲気が舞台を包み始めています。

■舞台セット設営

■姫の嫁入り道具を運ぶ荷車飾りにアイロンがけする福永さん
さあ、あと少し、今日は全体通しの「総練習」です。
今まで培ってきた「自分」を信じて演じきってください。役者も、スタッフも。
2017年11月28日
第9回きやま展開催中
第9回を数える「きやま展」が、基山町立図書館郷土資料コーナーで開催中です。
今年も、12月10日に公演される第2回きやま創作劇「八ツ並の姫」を深く知っていただくために、劇に関わる文化遺産や人をテーマに展示を行っています。
「八ツ並」とは何を指すのか?
何故、お姫様は観音様(観世音菩薩様)になられたのか?
など、むかし話に隠された人々の思いを展示しています。
劇を観てからでもよし、観劇する前に「予習」のために観るもよし。
創作劇で語られる一言ひとことのセリフの持つ意味を深く知るためにも、一度ご覧ください。
12月16日(土)午前10時からは、創作劇総指揮者である福永真理子さんによるトークも聞けます。
今回の公演までの道のりの中で、楽しかったこと、嬉しかったこと、辛かったことなど様々なお話が聞けることでしょう。
役者・スタッフの皆さん必見です。
会期:平成29年11月24日から12月17日まで
場所:中央公園内にある基山町立図書館郷土資料コーナー

今年も、12月10日に公演される第2回きやま創作劇「八ツ並の姫」を深く知っていただくために、劇に関わる文化遺産や人をテーマに展示を行っています。
「八ツ並」とは何を指すのか?
何故、お姫様は観音様(観世音菩薩様)になられたのか?
など、むかし話に隠された人々の思いを展示しています。
劇を観てからでもよし、観劇する前に「予習」のために観るもよし。
創作劇で語られる一言ひとことのセリフの持つ意味を深く知るためにも、一度ご覧ください。
12月16日(土)午前10時からは、創作劇総指揮者である福永真理子さんによるトークも聞けます。
今回の公演までの道のりの中で、楽しかったこと、嬉しかったこと、辛かったことなど様々なお話が聞けることでしょう。
役者・スタッフの皆さん必見です。
会期:平成29年11月24日から12月17日まで
場所:中央公園内にある基山町立図書館郷土資料コーナー

2017年11月26日
『八ツ並の姫 観音様になったお姫様』大ホール練習
夏から練習が始まった第2回きやま創作劇『八ツ並の姫』が、いよいよ町民会館大ホールでの練習へと入りました。
これから本番まで、第4コーナーを曲がりゴールめがけてラストスパートです。
怪我や病気に注意を払い、万全の身体で役者の皆さん、スタッフの皆さん、お一人お一人が持てる力を出しきりましょう!そうすれば、きっとあの笑顔がむこうからやって来てくれます。これまでのように。

■総指揮者 福永さんより、本番までの諸注意説明の様子
これから本番まで、第4コーナーを曲がりゴールめがけてラストスパートです。
怪我や病気に注意を払い、万全の身体で役者の皆さん、スタッフの皆さん、お一人お一人が持てる力を出しきりましょう!そうすれば、きっとあの笑顔がむこうからやって来てくれます。これまでのように。

■総指揮者 福永さんより、本番までの諸注意説明の様子
2017年10月09日
平成29年度歴史散歩 下見会
秋晴れの中、来年3月3日(土)に開催予定の基山・鳥栖・小郡クロスロード文化研究会(以下、「クロスロード文化研」と記載)主催の歴史散歩下見会が開催されました。クロスロード文化研の構成メンバーとして活動している本会と、基肄かたろう会のメンバーで参加し、今回の協働メンバーである鳥栖の郷土史関係団体の方々と実地検討を行いました。

■JR基山駅での事前説明の様子
今回は、これまで歩かなかった旧長野村(基山町長野)、旧奈良田村(基山町長野)や旧永吉村(鳥栖市永吉町)を巡るルートで、日本中世の荘園経営がなされた地を巡る歴史散歩として企画しています。
基山駅を出発し、元禄絵図に描かれている旧小倉村から旧長野村、旧奈良田村を巡り、鳥栖市に入り旧永吉村、旧幡崎村、そして旧姫方村を歩き、田代駅までをコースとして考えています。

■小倉にある老松神社

■南奈良田にある早馬社
解説場所の設定は、各旧集落にあるお宮を考えていますが、基山町のグループは「狛犬」の形が違う、竹の棒きれかと思ったら「キンドの守り」か!、この道は江戸時代からの道なんだ、この工場ができる前は一面田んぼだったよね、等興味の向くまま気の向くままに近くにおられた地元の方々の話に聞き入っていました。なかなか先へ進まない下見会で、今度の歴史散歩でも新たな文化遺産情報との「出会い」が期待できそうです。

■南奈良田にある日吉神社のキンドの魔除け

■JR基山駅での事前説明の様子
今回は、これまで歩かなかった旧長野村(基山町長野)、旧奈良田村(基山町長野)や旧永吉村(鳥栖市永吉町)を巡るルートで、日本中世の荘園経営がなされた地を巡る歴史散歩として企画しています。
基山駅を出発し、元禄絵図に描かれている旧小倉村から旧長野村、旧奈良田村を巡り、鳥栖市に入り旧永吉村、旧幡崎村、そして旧姫方村を歩き、田代駅までをコースとして考えています。

■小倉にある老松神社

■南奈良田にある早馬社
解説場所の設定は、各旧集落にあるお宮を考えていますが、基山町のグループは「狛犬」の形が違う、竹の棒きれかと思ったら「キンドの守り」か!、この道は江戸時代からの道なんだ、この工場ができる前は一面田んぼだったよね、等興味の向くまま気の向くままに近くにおられた地元の方々の話に聞き入っていました。なかなか先へ進まない下見会で、今度の歴史散歩でも新たな文化遺産情報との「出会い」が期待できそうです。

■南奈良田にある日吉神社のキンドの魔除け
2017年08月02日
『八ツ並の姫』が語る時代(その7)
仲の良かったお父さんたち(いわば、富豪たち)が、突如として仲違いをしてしまう。このような時代とは、これら地方の富豪たちを取りまとめる力・権力者が不在、もしくは弱体化している時代といえます。
奈良時代から平安時代中期までの時代で権力者とは誰か。といえば大和政権であったり、貴族社会を取りまとめていた王朝国家体制下の権力者である上級の権門と呼ばれた貴族たちです。奈良時代の大和政権下では、強力な律令体制に基づく官僚国家体制のもと、法と法の番人としての軍団、そして貴族たちを支える徴税制度という古代国家体制下にあり、地方の豪族層を官僚制度下に置いた郡司制が施行されていた時代です。宮都(天皇‐貴族)‐大宰府(多賀城)‐国衙(国府)‐郡家という階層の元、支配体制が敷かれていた時代とも言えます。ただし、天皇を頂点とする一元国家体制といえるものではなく、地方の豪族は地方の豪族を郡司として任用し、ローカル・ルールを用いつつ統治していくという二元国家体制であったと考えられています。
一方、平安時代中期という時代の王朝国家体制はこれらが崩れ、特定貴族に帰属し貴族層が有する権力・権威を後ろ盾として地方の豪族・富豪層が地域支配を強化していく時代にあたり、いわばその後に展開する群雄割拠の武士の社会への過渡期ともいえる時代に変化していきます。
ここまで記すと、『八ツ並の姫』が描く時代が、奈良時代の出来事なのか一方の極としての平安時代中期の出来事なのか、自ずと見えてきたのではないでしょうか。
そう、仲の良かったお父さんたち(富豪たち)が、突如として仲違いをする社会、人々を法のもとに抑え込んでいた奈良時代の物語ではなく、これら律令体制が崩れつつあった平安時代中期の一時期を表現した物語であると推定できます。
平安時代中期といえば、関東では平将門が特定貴族を後ろ盾とする社会に反旗をひるがえし「反乱」を起こした時であり、九州では藤原純友が大宰府を焼き払った「反乱」を起こした、まさにその時にあたっているのです。

第2回きやま創作劇「八ツ並の姫 観音様になったお姫様」が描く時代は、今から1000年程まえの平安時代中期の物語だったのです。

奈良時代から平安時代中期までの時代で権力者とは誰か。といえば大和政権であったり、貴族社会を取りまとめていた王朝国家体制下の権力者である上級の権門と呼ばれた貴族たちです。奈良時代の大和政権下では、強力な律令体制に基づく官僚国家体制のもと、法と法の番人としての軍団、そして貴族たちを支える徴税制度という古代国家体制下にあり、地方の豪族層を官僚制度下に置いた郡司制が施行されていた時代です。宮都(天皇‐貴族)‐大宰府(多賀城)‐国衙(国府)‐郡家という階層の元、支配体制が敷かれていた時代とも言えます。ただし、天皇を頂点とする一元国家体制といえるものではなく、地方の豪族は地方の豪族を郡司として任用し、ローカル・ルールを用いつつ統治していくという二元国家体制であったと考えられています。
一方、平安時代中期という時代の王朝国家体制はこれらが崩れ、特定貴族に帰属し貴族層が有する権力・権威を後ろ盾として地方の豪族・富豪層が地域支配を強化していく時代にあたり、いわばその後に展開する群雄割拠の武士の社会への過渡期ともいえる時代に変化していきます。
ここまで記すと、『八ツ並の姫』が描く時代が、奈良時代の出来事なのか一方の極としての平安時代中期の出来事なのか、自ずと見えてきたのではないでしょうか。
そう、仲の良かったお父さんたち(富豪たち)が、突如として仲違いをする社会、人々を法のもとに抑え込んでいた奈良時代の物語ではなく、これら律令体制が崩れつつあった平安時代中期の一時期を表現した物語であると推定できます。
平安時代中期といえば、関東では平将門が特定貴族を後ろ盾とする社会に反旗をひるがえし「反乱」を起こした時であり、九州では藤原純友が大宰府を焼き払った「反乱」を起こした、まさにその時にあたっているのです。

第2回きやま創作劇「八ツ並の姫 観音様になったお姫様」が描く時代は、今から1000年程まえの平安時代中期の物語だったのです。

2017年08月01日
『八ツ並の姫』が語る時代(その6)
むかし話『八ツ並の姫』が語る時代を探って6話目になりました。
さあ、『八ツ並の姫』が語る時代について、まとめに入りましょう。
少々長くなりますが、お付き合いください。
『八ツ並の姫』を構成している様々な言葉や物語の流れから推察して、この話が描く時代について奈良時代から平安時代中期、いわば基肄城が大和政権によって再整備され古代国家の成立として日本の歴史に刻まれた時代から、菅原道真公が亡くなられ源氏と平氏の権力争いが幕を開けようとする時代の話であるところまでつきとめてきました。
この西暦700年代から1000年代までの約300年間のどこに「八ツ並の姫」の物語は位置しているのでしょうか。
それを読み解く鍵は、物語にある次の件(くだり)にあります。
八ツ並長者と仲のよかった柳川長者の元へ嫁いだ八ツ並の姫。たいそう幸せな日々が流れていましたが・・・・・。
「世の中は本当にままならぬもので、両家の間に大変なことが起きてしまいました。」
「はじめのことのおこりと言うのは、わずかな土地のあらそいからでしたが、それが段々と大きくなって、とうとう両家は戦(いくさ)をすることになりました。」

■嫁いだ柳川の家の者たちから迫害をうけ、一人悲しむ姫
ここから想定される『八ツ並の姫』が語る時代とは、いつの時代の出来事なのでしょうか・・・・。
さあ、『八ツ並の姫』が語る時代について、まとめに入りましょう。
少々長くなりますが、お付き合いください。
『八ツ並の姫』を構成している様々な言葉や物語の流れから推察して、この話が描く時代について奈良時代から平安時代中期、いわば基肄城が大和政権によって再整備され古代国家の成立として日本の歴史に刻まれた時代から、菅原道真公が亡くなられ源氏と平氏の権力争いが幕を開けようとする時代の話であるところまでつきとめてきました。
この西暦700年代から1000年代までの約300年間のどこに「八ツ並の姫」の物語は位置しているのでしょうか。
それを読み解く鍵は、物語にある次の件(くだり)にあります。
八ツ並長者と仲のよかった柳川長者の元へ嫁いだ八ツ並の姫。たいそう幸せな日々が流れていましたが・・・・・。
「世の中は本当にままならぬもので、両家の間に大変なことが起きてしまいました。」
「はじめのことのおこりと言うのは、わずかな土地のあらそいからでしたが、それが段々と大きくなって、とうとう両家は戦(いくさ)をすることになりました。」

■嫁いだ柳川の家の者たちから迫害をうけ、一人悲しむ姫
ここから想定される『八ツ並の姫』が語る時代とは、いつの時代の出来事なのでしょうか・・・・。
2017年07月29日
第2回きやま創作劇「八ツ並の姫」配役決定!
本日午前、第2回きやま創作劇「八ツ並の姫 観音様になったお姫様」の配役が決定され、総指揮者である福永さんの最終確認の後、発表が行われました。

「希望通り!」「希望がかなわなかった」
劇に対する真摯な熱情とともに、個性が持つ力(話術、雰囲気、姿勢)と劇が持つ「姿」が合わさって、聴衆に感動を与えます。個性を出しすぎてもまとまりのないものになり、出さなさ過ぎても特徴のない「平板」な物語になる。これら様々な要素を生かし(活かし)創り上げていく総指揮者の苦難は計り知れません。
与えられた役を熟(こな)していくこと、字のごとく熟(じゅく)していく自らの新たな姿に、多様な「自分」を見つけるよい機会にもなります。
真っ新な「自分」というカンバス(CANVAS)に、総指揮者である福永さんが色を与えていくかのごとく、役者の皆さん、新たな自分見つけを劇で実現していってください。それも、劇の持つ「力」だと思います。
さぁ、役も見えてきました。自らのすべてを与えられた役に注ぎ込み、カーテンコールの拍手喝采をあびる自分の姿を目指して、みんなで進んでいきましょう。

「希望通り!」「希望がかなわなかった」
劇に対する真摯な熱情とともに、個性が持つ力(話術、雰囲気、姿勢)と劇が持つ「姿」が合わさって、聴衆に感動を与えます。個性を出しすぎてもまとまりのないものになり、出さなさ過ぎても特徴のない「平板」な物語になる。これら様々な要素を生かし(活かし)創り上げていく総指揮者の苦難は計り知れません。
与えられた役を熟(こな)していくこと、字のごとく熟(じゅく)していく自らの新たな姿に、多様な「自分」を見つけるよい機会にもなります。
真っ新な「自分」というカンバス(CANVAS)に、総指揮者である福永さんが色を与えていくかのごとく、役者の皆さん、新たな自分見つけを劇で実現していってください。それも、劇の持つ「力」だと思います。
さぁ、役も見えてきました。自らのすべてを与えられた役に注ぎ込み、カーテンコールの拍手喝采をあびる自分の姿を目指して、みんなで進んでいきましょう。
2017年07月04日
第2回きやま創作劇『八ツ並の姫 観音様になったお姫様』
去る7月1日土曜日午前10時から、基山町保健センターにて第2回きやま創作劇『八ツ並の姫 観音様になったお姫様』の第1回練習が行われました。

きやま創作劇実行員会の園木会長の挨拶の後、創作劇の素材となった「八並の娘」のむかし話から考えられる歴史性(時代性)について基山の歴史と文化を語り継ぐ会副会長より講話があり、その後、制作総指揮を執る福永さんによる台本読みが行われています。

今回の驚きは、いずれの時間も練習に集まった子どもたちが、真剣に聞き入り、そして真剣にメモをとる姿に、これまで積み重ねてきた創作劇制作の姿を回顧した時、演劇文化が基山に定着した姿を目の当たりにした気がしました。

午後からのセリフ合わせには、経験者、初めての方関係なく、皆の素養と役どころの合わせ(試し)が行われ、その中にも経験者の凄さや、初体験者の初々しさに感心させられました。

先輩の姿勢は良くも悪くも後輩の手本となり、後輩は先輩の姿から良し悪しを学ぶ姿勢も大切にしてください。
これら経験から学ぶことが歴史を学ぶことの原点です。
家族とは異なる多様な人びとで構成される「社会」に身を置く時、自らの役割を新たに確認し、多様さを受け入れる寛容さが芽生えてきます。それを十二分に裏付けてくれるこれまで集ってくださった多くの役者やスタッフの方々の姿を思い起こすに、創作劇の持つ社会的役割を改めて感じた日となりました。
さあ、練習開始です。与えられた役割を素直に受け入れ「演じきること。」が、参画した皆さんに与えられたミッションです。
カーテンコールの後、拍手の渦の中で公演の幕が下りた時の感動をイメージして、進んでいきましょう。
みんなで!

■紙芝居「観音様になったお姫様の話」より

きやま創作劇実行員会の園木会長の挨拶の後、創作劇の素材となった「八並の娘」のむかし話から考えられる歴史性(時代性)について基山の歴史と文化を語り継ぐ会副会長より講話があり、その後、制作総指揮を執る福永さんによる台本読みが行われています。

今回の驚きは、いずれの時間も練習に集まった子どもたちが、真剣に聞き入り、そして真剣にメモをとる姿に、これまで積み重ねてきた創作劇制作の姿を回顧した時、演劇文化が基山に定着した姿を目の当たりにした気がしました。

午後からのセリフ合わせには、経験者、初めての方関係なく、皆の素養と役どころの合わせ(試し)が行われ、その中にも経験者の凄さや、初体験者の初々しさに感心させられました。

先輩の姿勢は良くも悪くも後輩の手本となり、後輩は先輩の姿から良し悪しを学ぶ姿勢も大切にしてください。
これら経験から学ぶことが歴史を学ぶことの原点です。
家族とは異なる多様な人びとで構成される「社会」に身を置く時、自らの役割を新たに確認し、多様さを受け入れる寛容さが芽生えてきます。それを十二分に裏付けてくれるこれまで集ってくださった多くの役者やスタッフの方々の姿を思い起こすに、創作劇の持つ社会的役割を改めて感じた日となりました。
さあ、練習開始です。与えられた役割を素直に受け入れ「演じきること。」が、参画した皆さんに与えられたミッションです。
カーテンコールの後、拍手の渦の中で公演の幕が下りた時の感動をイメージして、進んでいきましょう。
みんなで!

■紙芝居「観音様になったお姫様の話」より
2017年03月04日
第10回 歴史散歩開催
本日、基山・小郡・鳥栖クロスロード文化研究会(以下「文化研究会」と記載)主催による第10回歴史散歩が開催され、好天にも恵まれたこともあり、総勢150名の方々が小春日和の中、歩かれました。

■開会の様子
本会の園木会長が文化研究会の会長を務められ、園木会長の挨拶からはじまり、本会ならびに基肄語ろう会も参画して、基山~小郡を舞台に、「みんなを見守ってきた神様・ほとけ様」と題して、木山口町から小倉村までの文化遺産を解説しています。

■初代郵便局長顕彰碑の前にて
木山口町にある町家建築や町の由来を記した板書が残る若宮八幡神社、対馬藩の東の端にある伊勢山神社など、身近なものからいつもは見ることができない文化遺産まで多様なものを基肄かたろう会の方々と解説しました。

■どろどろ参り祠前での解説の様子
一回一回の積み重ねで、調べ不足や語り不足な点も解説することで明らかになり、次回に活かす「糧」になったことと思います。
また、来年に向けて調べを進めますので、様々な点で気づきをくださった参加者の皆さまに感謝いたしますとともに、またお越しください。
ありがとうございました。
スタッフの皆さん、お疲れ様でした。

■開会の様子
本会の園木会長が文化研究会の会長を務められ、園木会長の挨拶からはじまり、本会ならびに基肄語ろう会も参画して、基山~小郡を舞台に、「みんなを見守ってきた神様・ほとけ様」と題して、木山口町から小倉村までの文化遺産を解説しています。

■初代郵便局長顕彰碑の前にて
木山口町にある町家建築や町の由来を記した板書が残る若宮八幡神社、対馬藩の東の端にある伊勢山神社など、身近なものからいつもは見ることができない文化遺産まで多様なものを基肄かたろう会の方々と解説しました。

■どろどろ参り祠前での解説の様子
一回一回の積み重ねで、調べ不足や語り不足な点も解説することで明らかになり、次回に活かす「糧」になったことと思います。
また、来年に向けて調べを進めますので、様々な点で気づきをくださった参加者の皆さまに感謝いたしますとともに、またお越しください。
ありがとうございました。
スタッフの皆さん、お疲れ様でした。
2017年02月27日
■歴史散歩開催
3月4日(土)、毎年恒例の歴史散歩を開催します。
今年のテーマは、「みんなを見守ってきた神さま、ほとけ様」と題して、JR基山駅から西鉄三沢駅までの5.6kmを歩きます。木山口町の成り立ちを知ることができる若宮八幡神社や、江戸時代からよく知られる黒岩稲荷神社、鎌倉時代末期の石仏を祀る祠など、人びとの暮らしを見守り続けた神さま、仏様を巡ります。

【歴史散歩リハーサルの様子 木山口町の若宮八幡神社にて】
参加申し込みは不要です。当日午前8時30分からJR基山駅西口ロータリー横にて受付を開始します。出発は午前9時から出発し、おおむね午後12時には西鉄三沢駅にたどり着けるよう散策します。

【歴史散歩リハーサルの様子 初代郵便局長顕彰碑の前にて】
あまり知られていない文化遺産もめぐります。是非、参加ください。
●少雨決行。
雨天時は、3月5日(日曜日)に延期します。
延期の決定は、当日午前7時に判断します。
(当日の連絡先 基山町役場 0942-92-2011)
●駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。
今年のテーマは、「みんなを見守ってきた神さま、ほとけ様」と題して、JR基山駅から西鉄三沢駅までの5.6kmを歩きます。木山口町の成り立ちを知ることができる若宮八幡神社や、江戸時代からよく知られる黒岩稲荷神社、鎌倉時代末期の石仏を祀る祠など、人びとの暮らしを見守り続けた神さま、仏様を巡ります。

【歴史散歩リハーサルの様子 木山口町の若宮八幡神社にて】
参加申し込みは不要です。当日午前8時30分からJR基山駅西口ロータリー横にて受付を開始します。出発は午前9時から出発し、おおむね午後12時には西鉄三沢駅にたどり着けるよう散策します。

【歴史散歩リハーサルの様子 初代郵便局長顕彰碑の前にて】
あまり知られていない文化遺産もめぐります。是非、参加ください。
●少雨決行。
雨天時は、3月5日(日曜日)に延期します。
延期の決定は、当日午前7時に判断します。
(当日の連絡先 基山町役場 0942-92-2011)
●駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。
2016年12月18日
第8回きやま みんなが守ってきた「きやま」展 展示解説
本日、午前10時より基山町立図書館郷土資料コーナーに展示している、「ホタル列車」が走った頃の近代の基山展についての展示解説、ならびに第1回きやま創作劇「ホタル列車」の総指揮者である福永真理子さんを迎えて、制作への思いを語っていただきました。

図書館多目的室にて、二部構成で行い、第一部は脚本監修者である当会の副会長による「ホタル列車が走った頃の基山」と題して講話を行い、第二部は、制作総指揮を執られた福永真理子さんから、ご苦労や喜びなどを語っていただきました。
■トークショーの様子(左手奥が、福永真理子さん)

「心の無い劇は、人には伝わらない。」「師匠から辛く当たられた頃」の話など、今の指導者福永さんがある背景の一端を知ることができ、とても有意義なひと時でした。
また、会場におられた方々の多くが、役者であったりスタッフを務めていただいた方々でしたので、司会から、①「福永先生の指導は、厳しくて、怖かったですか?」という問いに、お一方も手を上げられませんでした。また二つ目として、②「11日の公演が終わった後、心にぽっかりと穴が開いたようで、福永先生の刺激が欲しいと思われた方。」という問いには、幾人かの方が手を上げられました。まだまだ福永先生のご指導は手ぬるかったようで、もっと、もっと厳しいご指導を待っておられるのだろうと感じたところです。来年取り組むようになった暁には、竹製のムチを福永先生にご用意させていただきます。
1時間30分ほどの会でしたが、瞬く間に過ぎ去り、福永さんにはもっと、もっと語っていただきたいところでした。貴重なお話をお聞かせいただきましたこと、心より感謝いたします。ありがとうございました。
また、お集りいただいた皆様、ありがとうございました。
きやま創作劇は、一回、一回の積み重ねを大切にし、来年再び皆さまにお会いできることを、また新しい仲間と出会えることを楽しみにしております。

みなさん、ありがとうございました。
また、会いましょう!

図書館多目的室にて、二部構成で行い、第一部は脚本監修者である当会の副会長による「ホタル列車が走った頃の基山」と題して講話を行い、第二部は、制作総指揮を執られた福永真理子さんから、ご苦労や喜びなどを語っていただきました。
■トークショーの様子(左手奥が、福永真理子さん)

「心の無い劇は、人には伝わらない。」「師匠から辛く当たられた頃」の話など、今の指導者福永さんがある背景の一端を知ることができ、とても有意義なひと時でした。
また、会場におられた方々の多くが、役者であったりスタッフを務めていただいた方々でしたので、司会から、①「福永先生の指導は、厳しくて、怖かったですか?」という問いに、お一方も手を上げられませんでした。また二つ目として、②「11日の公演が終わった後、心にぽっかりと穴が開いたようで、福永先生の刺激が欲しいと思われた方。」という問いには、幾人かの方が手を上げられました。まだまだ福永先生のご指導は手ぬるかったようで、もっと、もっと厳しいご指導を待っておられるのだろうと感じたところです。来年取り組むようになった暁には、竹製のムチを福永先生にご用意させていただきます。
1時間30分ほどの会でしたが、瞬く間に過ぎ去り、福永さんにはもっと、もっと語っていただきたいところでした。貴重なお話をお聞かせいただきましたこと、心より感謝いたします。ありがとうございました。
また、お集りいただいた皆様、ありがとうございました。
きやま創作劇は、一回、一回の積み重ねを大切にし、来年再び皆さまにお会いできることを、また新しい仲間と出会えることを楽しみにしております。

みなさん、ありがとうございました。
また、会いましょう!
2016年12月12日
「ホタル列車」 感動をありがとう!
感動をありがとう!
再び走りはじめた、きやま創作劇。
昨日、11日(日)、第1回きやま創作劇「ホタル列車」の公演が、満員のお客様を迎え行われました。
笑いあり、歌あり、そして涙あり。

かつて基山の秋光川にあった九州帝国大学源氏螢養殖場と、そこで育った螢たちを観光資源として、博多方面から基山に走った「ホタル列車」を、基山町民の手で、力で、基山町民会館大ホールの舞台に蘇らせました。


「ホタルのともし火は、平和の証、平和の証やけんな!」
老いた正吉が最後に叫びます。
今を生きる私たちに課せられた「平和」を維持すること。
昨今の情勢を見ると、簡単なようで、難しい課題です。
でも、世界に生きる一人、一人が願い、希求することで叶えられるものだとも思います。
この創作劇は、8月から練習を始めました。
昨日の公演で結実し、演じきった顔、顔、顔には、達成感と安堵の表情で一杯でした。2回の公演を演じきった役者の皆さんの姿を観て感じたこととして、お一人おひとりに基山のご先祖さまたちが降臨し、セリフから自らの言葉へと変化していく様を見たようでした。

役者として、スタッフとして、そして関係された多くの方々のお力添えで、まさに互いのできることを持ち寄って昨日の公演を無事終わることができました。心より深く感謝申し上げます。
制作総指揮を執られた福永真理子さん、お疲れさまでした。
そして、皆さん、ありがとうございました。
再び走りはじめた、きやま創作劇。
昨日、11日(日)、第1回きやま創作劇「ホタル列車」の公演が、満員のお客様を迎え行われました。
笑いあり、歌あり、そして涙あり。

かつて基山の秋光川にあった九州帝国大学源氏螢養殖場と、そこで育った螢たちを観光資源として、博多方面から基山に走った「ホタル列車」を、基山町民の手で、力で、基山町民会館大ホールの舞台に蘇らせました。


「ホタルのともし火は、平和の証、平和の証やけんな!」
老いた正吉が最後に叫びます。
今を生きる私たちに課せられた「平和」を維持すること。
昨今の情勢を見ると、簡単なようで、難しい課題です。
でも、世界に生きる一人、一人が願い、希求することで叶えられるものだとも思います。
この創作劇は、8月から練習を始めました。
昨日の公演で結実し、演じきった顔、顔、顔には、達成感と安堵の表情で一杯でした。2回の公演を演じきった役者の皆さんの姿を観て感じたこととして、お一人おひとりに基山のご先祖さまたちが降臨し、セリフから自らの言葉へと変化していく様を見たようでした。

役者として、スタッフとして、そして関係された多くの方々のお力添えで、まさに互いのできることを持ち寄って昨日の公演を無事終わることができました。心より深く感謝申し上げます。
制作総指揮を執られた福永真理子さん、お疲れさまでした。
そして、皆さん、ありがとうございました。